
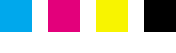

Idolm@ster 小説『歌姫咲く花の園』
九
少しの間、貴音が何と言ったのか理解出来なかった。
いや、理解したくなかった。
だが、伊織の利発な思考はそれを許さず、いやがおうにも貴音の発した言葉を脳に刻みつける。
貴音の瞳が真っ直ぐに伊織の瞳を見ている。
貴音は反論の言葉があるかとも思ったが、伊織は逆に押し黙ってしまう。
薄暗く狭い書庫には、ひっかくような静寂が渦巻いている。
伊織も貴音の瞳を見つめ返してはいるが、それは見つめ返していると言うよりも、目を逸らす事が出来ないと言った方が正しかった。
事実、今の伊織はまさしく蛇に睨まれた蛙の状態同然。
足が竦み、心臓は早鐘と化している。
だが、伊織にとっては心臓が止まりそうな気分。
「……」
僅かに残った自尊心がせめて毅然としようとするが、そう思えば思う程体から力が抜けていく。
伊織は重力を失ったかのようにふらつき、そしてそのまま後ろにつんのめり、倒れる。水の中に沈むみたいにゆっくりと。
貴音は、はっと駆けだし伊織を抱き抱えるように支えた。
何と軽く、そして柔らかな少女か。
貴音は怯える伊織を立たせ、そして後ろ手に持っていたファイルを手に取る。
抵抗は無かった。
机の上には事務所の書類が並び、中も綺麗にファイリングされている。
手に取ったそれを開いている場所に置くと、見事に仕分けが揃った。
書類は少ないとは言え、さぞ大変だっただろう。
こんな地味な事を、このきらびやかな少女は一人、埃にまみれながらやっていたのか。
「……」
伊織はもうなすがままとなり、貴音を見る事しか出来ない。
貴音は再び伊織に視線を戻す。
途端、叱られた子供のようにして視線を床に逸らす伊織。
水瀬伊織。この少女は…。
貴音は何か言い様のない感情が、自分の中に匂い立つように沸き上がるのを覚える。
少しの後。
「は、離して…」
ようやく、もう耐えられない、とばかりに弱々しい声が聞こえる。
気付くと、貴音はずっと伊織の手首を掴んだままだった。
「…失礼」
貴音が手から力を抜くと、伊織はゆっくりとした動きで腕を下げた。
離された腕を手で包み、伊織は俯く。
「貴女は、いつもこのような事を?」
貴音が少し屈み、伊織に視線を合わせて問う。
「…そうよ」
貴音の顔が近づき、僅かに身を竦ませるが、それでも伊織は辛うじて質問に答えた。
その声は明らかに震えている。
だが、視線こそ合わせないが、それでも足を踏ん張り、体だけは貴音に向き合わせている。
「……」
貴音は少しの間伊織の顔を見つめ、そして静かに呟く。
「どうやら、わたくしは貴女の事を見直す必要がありそうですね」
その言葉に伊織ははっと顔を上げ、そして感極まった声で怒鳴った。
「滑稽って…滑稽って、言ってたじゃないのっ!」
伊織は完全に馬鹿にされたと思い、いよいよ耐え切れなくなり外に飛び出す。
貴音は待って、と言いかけて手をあげるが、そのまま手を止めて視界から消える伊織を見送った。
「…貴女は、逃げなかった。それを認めたのです」
先程自分が問い詰めたときにも安易に逃げようとせず、留まっていたのだから、と貴音は目を伏せた。
その日から二日。
あれから伊織は事務所に姿を見せなかった。
困ったのは高木である。
何故なら、いくつかあるスケジュールの中に一つ、伊織に受けてもらいたい仕事があったのだ。
「やっぱり、電話に出てくれなくて…」
小鳥が受話器を置き、小さく溜息をついた。
「小鳥嬢、申し訳ありません」
貴音が頭を下げた。
「え? 貴音ちゃんがどうして?」
「私が追い詰めたのですから。伊織を」
「…貴音ちゃん」
あの日、奥から飛び出してきてそのまま出て行った伊織を見た小鳥は、何も言えなかった。
あの時、伊織は泣いていた。
だが、その後部屋から出て来た貴音も、涙こそ流してはいなかったが、その表情は伊織と同じかそれ以上に悲しみ、切なさにまみれていたのだから。
「ともかく、あの子に非はありません」
「ふむ」
高木が顎を撫でながらうーん、と天井を見上げる。
「だが、仕事を断る訳にもいかん。仕方がない。そうだな、ここは一つ、春香くんに話を」
「時間を下さい」
貴音が普段よりも強い口調で高木の言葉を遮る。
「ん? 何かあるのかね?」
「わたくしが説得します。そのお仕事、確かご返答は四日後まででしたよね」
「そうだが…よく知っているね」
高木の言葉に、貴音が机の上にあったファイルを手に取る。
「この整理されたファイルのお陰で、一目で分かりました」
「おお、それは伊…あ、いや、ごほん、そうだな、そのファイルはとても見やすい」
高木が何かを言いかけて大仰に咳払いする。
「社長、ご心配なく」
貴音は柔らかく微笑む。全て知っている。そう語る瞳で。
「む、そうか…。ばれていたか。うむ、まぁ時間の問題とは思っていたが…」
「社長、一体いつからだったのですか?」
どうせなら全て知りたい。そう願っている瞳で貴音が問う。
「うむ、まぁ、彼女が話を持って来たときは少々驚いたよ。こんな地味な事をあれだけ熱心に、どうしてもやりたいと要望してきたのだからね。普段の彼女が望んでいる仕事とは対極の内容だと言うのに。言い出したのは…彼女が事務所に入って二ヶ月後くらい。丁度、彼女がトリのコンサートを開いた後だったな」
「…成る程」
「何か思い当たる節があるのかね?」
「恐らく、ですが。きっと伊織は、責任感を、自意識を、確かなそれを持ち始めたのだと思います。初めて人前で歌う。それがどういう事か、と。それをきっと考え始めたのでしょう」
「それは、いい事だね」
「ですが、それ故に彼女は自分が許せなくなったのでしょう」
「負い目を、感じたのだろうな。彼女はああ見えて相当に真面目な考えの持ち主だ」
貴音は頷く。
「伊織ちゃん…きっと今も悩んでいるんでしょうね」
小鳥が呟く。
貴音は暫くファイルを見つめ、そして顔を上げる。
「行ってまいります」
貴音が小鳥へ声をかける。
「あら、どこへ?」
小鳥が問いかける。
「無論、水瀬伊織の屋敷へです」
「そう。気をつ…」
えっ? と顔を上げた小鳥の視界には、既に貴音の姿は無かった。
「お嬢様」
部屋の外から新堂の声が聞こえる。
でも、私はどうしてもその声に応える気になれなかった。
「お嬢様、どうか出て来てくださいませんか?」
悲しそうな声。
でも…やっぱりごめんなさい。私に今、それは出来ない。
私は心の中で呟く。
うさちゃんを抱きしめる手に力がこもっていた。
ごめんね、ちょっとつぶれちゃってるかな?
少しして、静かな足音が部屋の前から遠ざかっていった。
「やめちゃった方が…いい…のかな…」
そう思ってなんかいない。
でも、そう思ってしまう。
私は、自分の心が自分ではないような、そんな不思議な感覚に戸惑っていた。
自分は何をしたくて芸能界に入りたいと思ったの?
自分は何が楽しくて芸能界でやっていこうと思ったの?
そして、誰の為に?
私が私に問いかけている。
その自問自答は、何一つ答を得られぬままに無限に積み重なっていく。
頭が痛い…。
まるで月のものが来たときのような鈍痛が頭を締め付ける。
やだな。
私はうさちゃんを抱きしめ、そのまま背丈の半分程もある大きな枕を頭にかぶって身を縮めた。
それから、どれ程の間そのままの時間が過ぎたんだろう。
再びノックの音が聞こえた。
今度こそ返事をしなくちゃいけない。
そう思って頭を上げた私の耳に、想像だにしなかった声が聞こえた。
「伊織。入れて下さる?」
思わず悲鳴を上げそうになる。
「ひ…。た…っ!。た、貴音!?」
「ええ」
「ど、どど…どうしてっ!?」
自分の声じゃないみたいなうわずった声が出た。
やだ、恥ずかしい。
「話があるからです。どうぞ入れてくださいませ」
「ち、違う! なんで? どうやってここに来たのよ?」
「お嬢様のご友人ですのでお通ししましたが…何かご都合のよろしくない事でも?」
扉の向こう。新堂が代わりに応てくれた。
友人? 貴音が? 私の? 友達? って、friend、の友達? amigo、の友達? amicus、の友達の事?
その単純な単語が理解しきれず、私は一気に頭を混乱させる。
「わ、え? あ…う、うん。そ、そうよ! ちょ、ちょっと待って!」
とりあえず慌ててベッドから飛び起き、シーツの乱れを整えて髪も直す。
そしてうさちゃんを隣に座らせる。
うさちゃん、大人しくしててね。
って、あれ? 何で私、貴音を部屋に入れる気満々なの?
追い返したっていい筈なのに。
なのに。
「…いいわよ」
ベッドに腰掛け直して、私はそう言っていた。
ちょっと待って!?
何でそう言っちゃう訳!? 誰? どの私がそう言っているの?
そんな事を考えながら混乱したままの私が居る部屋に声が響く。
「失礼」
今更だけど…貴音よね。この声。
そして、ドアが開いた。
「……」
「お元気そうですね」
真っ直ぐな瞳が私を釘付けにする。
ああ。
貴音だ。
やっぱり。
逃げる気は無い。
そう思ってはいた。にしても、何かあったらここがある。
ここに居れば…。
そう思っていたその場所にも、貴音はあっさり入って来た。
来ちゃった…。
軽いめまい。
そして何かがぷつんと切れたような気分。
私、なんだか一瞬、体が軽くなった気がした。
気分も。
うん。
「…何か、用かしら?」
ベッドに座ったまま、私は問いかけた。
そっと、うさちゃんの手を握りながら。
「用、という程の用では無いのですが…。少々、お話をしたいと思いまして」
「そう。どんな?」
こういう状態、なんていうのかしら。
まな板の上の鯉…じゃなくって、年貢の納め時…でもなくて、ああ、そうそう、覚悟だわ。覚悟を決めたって言うのね。こういうの。
そう悟った私は、なんだかさっきまでの混乱が嘘みたいに落ち着いて会話が出来ていた。
ちょっと、自分で自分を偉いと思ったわ。
ちょっとだけね。
「では、失礼いたします。後でお茶をお持ちいたします」
貴音と私の会話の状況を確認してから、新堂が出て行った。
私と二人きりにして大丈夫かを、確認してくれたのよね、これって。
ほんと、新堂ってさりげなく、そして絶妙に気を利かせてくれる。
いつもの事だけど、感謝してるわ。
「よろしいですか?」
私の前に立つ貴音が問いかける。
視線は私の隣。
「いいわよ」
「では」
そう言うと、貴音は私の横に座った。
と、思ったら。
「あっ」
小さく声を上げて、貴音はころりとベッドに仰向けになってしまう。
「…何してるの?」
「失礼。思ったよりベッドが柔らかくて」
ああ、バランス崩しちゃったって事ね。
いつも通り、流れるような動作でだけど、気持ち、慌てて起き上がった気がする。
そんな柔らかかったかしら? このベッド。
「良いベッドですね」
「そう? いつも寝ていると、分かんなくなるけど」
「それも、良いベッドの条件です」
何で貴音が言うと何でもない一言も含蓄のありそうな言葉になるのかしら。
今度聞いてみたいわ。
「…それで、あんたがここにまで来るなんて、一体何?」
私は問いかけた。
聞きたく無い気はしたけど、あっちから言われるとますます良くない。
そんな気がしたから。
「お仕事の打ち合わせ、でしょうか?」
「…え?」
ちょっと、質問に質問で答えるのは良くないのよ。
「四日後、ケーブルテレビ局のCF撮影があります。水瀬伊織、貴女にはそのCFに出演してもらいます」
「はい?」
あ、私今すっごい間抜けな顔したかも。やだ。
私は思わずうさちゃんを抱き上げてしまう。
「今言った通りです。貴女ならご存じの筈ですよね。貴女の整理した書類の中にあった仕事です。スケジュールも存じていると思いますが」
「…く、区のケーブルテレビ局のCFの事でしょ? あれ、確かに四日後に自社テレビ局の第二スタジオでってなっているけど…。それ、別に私のじゃ…」
「貴女の仕事なのです。高木社長が困ってましたよ。あなたが来てくれない、と。あなたへのオファーなのですよ」
「仕事…私が…。でも、オーディションとか受けてないのに…」
そう、最近の私はオーディションを受けてない。
だから、仕事がある筈がない。
とすれば考えられるのは…。
「出来ない…そんなずるい事…」
考えられるのは、一つだけ。
私の事を使うように、何かコネが動いた…。
そんな事をして仕事に、テレビに出たと知られたら、ますますみんなに顔を見せられない。
ますますみんなから取り残される。
もう、とてもみんなに会えなくなる。
頭の中に溶けた鉛が流し込まれたみたいに重い気持ちがのしかかってきた。
うさちゃんを抱きしめる腕に力が入る。
ごめんね、今日は潰しちゃってばっかり。
「自惚れないでください」
突然、闇を切り裂くような鋭い声が私の脳天に突き刺さった。
息を呑んで顔を上げた私を、鋭い瞳の貴音が睨んでいる。
今までで一番怖い顔で。
「貴女はその程度ですか?」
「な、何が…」
「貴女は、自分をその程度と思っているくせにアイドルになりたいと思っていたのですか? と聞いているのです」
言葉が突き刺さる。
私はなにも言えなかった。
「貴女には確かに他の子よりは事務所やテレビ局的にコネのようなものはあるでしょう。しかし、局もそこまで零細企業ではありません。貴女のような海のものとも山のものともつかぬアイドルの卵にそこまで尻を振る程暇でもなければ、貴女にはその魅力も今はありません」
心臓がまた止まるかと思った。
貴音の言葉が、私の心に、私の心の中の何かに突き刺さる。
目を閉じられない。
閉じたら、きっとこぼれちゃうから。
涙が。
「だ…。なら…どうして…私なんかに仕事が…」
貴音の手が急に振り上げられた。
私は何をされるか理解して思わず目をつむる。
途端、瞳にいっぱい溜まっていた涙が弾けた。
歯を食いしばり、きっとやって来る痛みに、ほっぺの痛みに耐えようとした。
うさちゃん、助けて!
でも…。
次に、私の頬に感じたのは、痛みじゃ無かった。
それは、私の頬を包み込む貴音の暖かな手の感触。
ぶたれたんじゃない。
その事実に私は力が抜け、真っ暗な視界のままで倒れ込む。
ううん、貴音が、確かに貴音が私の肩を持って、引き寄せていた。
私の顔に柔らかくて温かいものがあたる。
甘いような涼しげなような、不思議な、でも落ち着く香りが鼻腔を満たす。
私…今…貴音に…?
恐る恐る瞳をあけると、そこは貴音の胸の中だった。
「…どうして…」
情けないくらい震える声で私は問いかけた。
「もう一度言います。これは、貴女へのオファーです。誰から言われたのでも、仕方なしなのでもありません。局の意志で、貴女へ指名があったのです」
「……」
私に…指名?
「単純な事です。貴女のステージを見た局が、貴女に興味を示した。貴女に任せて良いと判断した。貴女を必要とした。ただ、それだけです」
「…私に…私を…。私を…必要…」
私は恐る恐る顔を上げた。
目と鼻の先に、貴音の顔がある。
そこにあるのは怖い顔じゃない。
慈しむような、切なくなるような微笑みの貴音。
でも、その瞳がキッと変わる。
いつもの貴音の瞳に。
「水瀬伊織。聞きますが、貴女は、アイドルとして自分を磨きたいと思っていますか? それとも、そのままの意味の『偶像』として虚像扱いで終わりたいのですか?」
「わ、私は…」
頭の中に数え切れない単語が、情景が、色や音が駆け巡った。
でも、その中に何にも混ざらず、掻き消されない何かが浮かんでいる。
私は、それが何か分からないけど、でも、それがとても大切なものなのだと、それだけははっきり理解していた。
「私は…」
貴音を見る瞳が、自分でも強く、真っ直ぐになったと分かる。
だって、見詰め返す貴音の瞳に、その私が映っているから。
私を瞳の中に写す貴音が、とても満足げに見えたから。
「貴音」
「はい」
「私は、こんなところでくすぶっているタマなんかじゃないわよ」
今の私はきっと笑みを浮かべている。
うさちゃんを抱きしめる腕に力がこもる。
でも、それはさっきまでの逃げる為のものじゃない。
決意。
見まごう事のない決意。
「では、どうしますか? 水瀬伊織」
「えーと…」
頭の中に、はっきりと何かが見える。
でも、それが何なのか。それが分からない。
ああもう、もどかしいわね!
「ど、どうもこうもないわよ! この伊織ちゃんの魅力に気付いたって言うならそれに応えるのがアイドルってものよ。受けるわ。まずは伊織ちゃんの魅力を全世界に向けて発信する足がかりとして、何だってやるわよ! あ、色物以外でね」
「受けるのですね? お仕事を」
「ええ! 任せておきなさい!」
「…どうやら、杞憂だったようですね」
「ん?」
「いえ、貴女は、やはり…」
貴音はそう言ってもう一度あの微笑みを見せてくれた。
「……」
その笑みを見た途端、もう一度私の中で緊張の糸が切れる。
「…貴音」
「はい」
「…ありがとう」
私は思わず感謝の言葉を紡いでいた。
「来てくれて…ありがとう」
いけない。今ふっきったと思ったのに、また泣き虫の私が出て来そう。
また瞳に溢れそうになった涙を隠そうとしたのに、それより先に私の瞳から涙がこぼれてしまった。
思わず俯く。
いけない。また心配させちゃう。また不安にさせちゃう。
どうしよう。
そう思っていた時。
「伊織、少々喉が渇きました」
「え?」
飲み物? と思って顔を上げた時、貴音の唇が目の前にあった。
目元に、貴音の唇が触れる。
すぐに離れたけど、今、間違い無く貴音の唇が触れた。
「……」
私は思わず呆けてしまった。
今、貴音が、私の涙を…?
「貴女の決意、しっかり味わわせていただきました」
「ち、え、あの…」
あんた、今何したの? 何したの? ねぇ?
「明日からスパルタですよ。何と言っても四日後ですから。覚悟しておいてください。では、明日の十時にスタジオで。用意はしておきます。着替えを忘れないように」
そう言って貴音は立ち上がる。
「伊織」
数歩歩き、振り向いた貴音が私の名を呼んだ。
「……」
「わたくし、負けませんよ。頂点を目指す者同士として」
「…うん」
今、何かすっごいライバル宣言された? なのに、私は馬鹿みたいな返事しか出来なかった。
「またね…」
そんな私の腑抜けたような間抜けな返答を聞いた貴音は、それでも満足げに微笑んで部屋を出て行った。
少しして新堂が入って来る。その手にはジュースのトレイを持って。
「貴音様はもうお帰りでしたか」
ああ、そこで会ったのね。
「うん」
「…顔が赤いようですが?」
そう聞いた新堂のその顔は、でも、心配している顔じゃなかった。安心の表情。
「うん」
「どうやら、宜しい事があったのですな」
そっと微笑む新堂。
新堂って、何でも分かるのね…。
「うん」
ああ。ダメ。頭が回らない。
「ちょっと、寝るわ…」
「はい。では、どうぞごゆっくり」
そう言って新堂は部屋を出て行った。
一人になった私は、力尽きたみたいに仰向けにベッドに倒れ込む。
て言うか、実際もう力尽きていたけど。
何も考えられず、私は少し眠った。
「ん…」
ふと、目が覚めた。
何分くらい眠ったの?
壁の振り子時計を見ると、どうやら三十分くらい眠ったみたい。
ああ、なんだかスッキリしたわ。
そして、その途端、いろいろな感情がまた心の中に渦巻き始める。
「私…やっぱりなりたい。アイドルに…」
心の吐露がそのまま口から流れ出ていた。
うん。
そうよ。
それだけの事だわ。
私は、アイドルになりたい。
理由は色々あるけど、それは、きっかけって言うだけ。
それが何を意味するのか。
そんなのを考えている暇があったら、ダンスレッスンでもボイスレッスンでもしている方がよっぽど健全だし有意義だわ。
伊織、あんたはあんたのやりたい事をやればいいのよ。
今は見えなくても、そのうち『それ』は見えてくる。
さっきまで心の中に見えていた『それ』が、きっと見えてくる。
だから、私はアイドルを目指すの。
『それ』が、アイドルになれって言っている。
私にはそれが相応しいって言っている。
だから、私はアイドルを目指すわ。
自分の力で、自分の努力で、自分の魅力で。
心の中の『それ』が熱いくらいに光った。
私は飛び起きて携帯を手に取ると、迷わず電話をかけた。
「もしもし、小鳥? 何でもいいわ。レッスンスタジオ何か開いている? 開いていたらすぐに入れて。…そう、ボイスレッスンがいけるのね。いいわ。直接これから行くから。え? スタートが二十分後? だから何? 今すぐ行くわよ。間に合わせるわよ。三分で行くから。ええ。それじゃよろしくね」
私は携帯を切ると同時に走り出した。
「びっくり…。すっごい元気なんだもん」
事務所。
小鳥が目を丸くしながら、レッスンの予約を入れていた。
「きっと、きっと伊織ならそうくると思っていました」
小鳥の前のソファ。
貴音が満足げに微笑んでいた。
「本当に電話が来るなんて、びっくりよ」
小鳥も嬉しそうに言う。
「では」
「あら、どこへ?」
「小鳥嬢、レッスンをペアに変更お願いします。ここからなら、少し急げばレッスン開始まで間に合いますよね?」
「あら」
小鳥は了解、と微笑んだ。
「新堂! 新堂−!」
「ここに」
呼んだ途端に新堂が顔を出す。
まるで、待っていたみたいな素早さで。
「車お願い! 今から三分でレッスン場に行きたいの」
「お任せを」
新堂は自信満々に応えた。
頼りにしているわよ。新堂!
私は廊下を駆け出した。
止まらない。
もう私は止まらない。
だって、私は水瀬伊織よ!
この伊織ちゃんが、止まる訳無いわ!
自身も根拠もない。
でも、私はそう信じる事が出来た。
理由は後から考えればいいわ。
「いってきまーす!」
私は青空の下へ飛び出した。
雲一つ無い空の下へ。
私の羽ばたく世界へ!
八へ Top 最終話へ

