
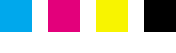

Idolm@ster 小説『歌姫咲く花の園』
八
少し、落ちついてきたのが分かる。
やよいの家についてから暫くして、私はようやく、自分のした事がなんだったのか、落ちついて思い直せるようになってきていた。
そう思うと、さっきまでなくなっちゃったみたいに麻痺していた体の感覚も少しずつ機能を回復し始める。
さっきやよいが渡してくれたハンカチで目をそっと拭い、視界が戻った目で部屋を見渡す。
木造。
なんだか時代のついたお部屋。
畳もちょっと日焼けしているわ。
部屋の規模は…まぁ、アレね。でも、なんだか落ち着く感じがする。
白くて、ちょっと茶色っぽい塗り壁にはカレンダーやらポスターやらがたくさん張ってあって、しかも、なんかシールも多い。
子供のハートをキャッチするアニメとか、星を護るヒーローとかって、ほんとにどこにでも浸透しているのね。そう言う意味ではすごいと思う。私も、そんな風になれるのかしら…。
なんだか、こういう風景ってちょっと昔のドラマのお茶の間風景にあった気がするわ。
あ、別に馬鹿にしてるとかじゃなんだいから。
ただ、普段身近にないからそう思っただけ。
全然嫌な感じはしないし、むしろ経験したことは無いはずなのに懐かしいような奇妙な落ち着きすら感じちゃう。
ああ、やっぱり私も日本人のDNA、持っているのかしら。
そんな不思議な風景に包まれて、私は自分が昔の世界に迷い込んだみたいな、おかしな気分になった。
視線を巡らせると、突然私がいた。
ちょっとびっくりしたけど、それはポスター。
私が初めてステージで歌った時のあのポスターだった。
やよい、わざわざ私のポスターを貼っていてくれたのね。
なんだか、嬉しいようなむずがゆいような、不思議な気分。
それに、人の家って、やっぱりみんな違う匂いなのね。
嫌な匂いじゃないけど、嗅いだ事のない、僅かに香るそれを感じると、なんだかそれも不思議な気分を沸かせる。
ああ、他の人の家にいるんだわ。
考えてみると、こうして友達の家に居るのって、ずいぶん久しぶりな気がする。
普段はお呼ばれしても客間とかホールとか、一緒に外で会ったりとかが多いから、こんな風にちゃんと人の家に上がるのって本当、久しぶり。
やっぱりこういうお付き合いがいいな。
「伊織ちゃん、ちょっとは落ちついてくれました?」
ずっと隣に居てくれたやよいが声をかけてきた。
「…うん、なんだか、とっても落ちついてきたわ。ありがとう」
私はやよいを見て微笑む。
大丈夫よね? 強ばったり、変な顔になって、ないわよね?
「えへへ、伊織ちゃんはやっぱり笑顔がいいですよ。みんな、笑顔が一番です」
みんな。
その言葉を聞いた時、頭の中に一人の顔が浮かび上がった。
「…千早」
思わず呟いたその言葉にやよいがハッとするのが分かる。
「……」
私も自分で自分の言葉にどきりとした。
「…伊織ちゃん」
やよいが囁くようにして私の顔をのぞき込む。
「あの、まずは、気分転換しませんか?」
「…気分転換?」
やよいが提案してきた。
…うん、気分転換…しなくちゃいけないんだろうけど…。
私は今の自分にそんなことが出来るかどうか自信がない。
ああ、いつもの私が私を見たら笑うのかしら? それとも失望する?
自分でもそう思うくらい今の自分は情けない。
人に嫌われるなんて、そりゃ別にしょっちゅうとは言わないけど、でも、そういう経験が無い訳じゃない。
それでも、誰かと喧嘩したことでこんなに落ち込むなんて、こんなに悲しくなるなんて初めて。
後悔と自責が、どうしても頭から離れない。
誰か、助けて…。
私は知らず知らずのうちにやよいの腕を握っていた。
「伊織ちゃん、私はずっと側にいますから。安心して下さい」
やよいはそう言って手を握ってくれた。
ありがとう。
私はその気持ちを表す事すら出来ず、ただ握り返すしか出来なかった。
伊織、もっとしっかりしなさいよ。
こんなんじゃ、芸能界でやっていけないわよ?
「小鳥さん、千早ちゃんはどうですか?」
765プロ事務所。
スタジオから引き上げてきたあずさが、今も仮眠室に籠もったまま出てこない千早のことを案じていた。
「そうね、まだ…ちょっとね」
小鳥が時計を見て言った。
あの後、レッスンを切り上げたみんなは一旦解散となり、貴音とあずさが事務所へ戻っていた。
「困りましたね…」
あずさが呟く。
「それは、何がですか?」
貴音が問う。
「…全部、ですよ」
あずさは当然です、と答えてそっと微笑んだ。
「そうですね」
貴音も柔らかく微笑み返す。
「先程、社長から何かお話があったようですね。なんて?」
あずさが小鳥に聞く。
「ええ、伊織ちゃんと千早ちゃんの、一週間後のライブの事で…」
「今回の件、出来るだけ、決め事は待ってもらえると嬉しいのですが」
貴音が静かに、しかしはっきりとした口調で呟いた。
「それは、勿論です。社長も、せっかくのこの晴れの大舞台。下手なことはしたくないと言っていましたし、あの二人への期待は、今も変わってはいません」
小鳥は社長を信じてください、と二人を見詰めた。
「…ちょっと、二人の我が強かったかなぁ」
そんなやり取りを聞いていた者が居た。
ソファに座って話を聞いていた律子が、ぼそりと呟く。
「我、ですか」
「…それは、ありますわね」
あずさと貴音が頷いた。
「秋月律子」
ふと、貴音が律子に近づく。
「んー?」
立ったままで見下ろしながら、貴音は問いかける。
「今回の件について、貴女から何かおっしゃりたい事は無いのですか?」
視線は問いかけと言うより問い詰めだった。
「どゆこと?」
律子はそんな貴音の目を、真っ直ぐに見据えたままで問い返す。
「いえ。ただ、今回の件は、そもそも始まりに貴女の一家言が、どうやら色々関わっているようですので」
貴音の声は落ち着いていた。だが、その視線は鋭く、重い。
「一家言なんておおげさな事言ってないわよ。ちょっとした提案程度、ま、ステップアップの為の試練、って言うと大げさかな」
「…秋月律子」
貴音の声が低くなった。
「あの子を試すような真似は、やめてください」
空気がしびれる様な緊張感が流れた。
「私は、あの子の可能性を信じている。心から。ただ、それだけだよ」
律子は貴音の視線に正面から向き合って言った。
眼鏡の奥、静かに輝くその瞳に迷いは無い。
五秒かそこらの沈黙が、何時間かにも感じられた。
「そうですか」
貴音はそれ以上問わず、窓の外へ視線を外す。
視線を外された律子はふぅ、と小さく溜息をついた。
内心は緊張していたようである。
そして、不安げに自分達を見ていたあずさを見て、何でもないですよ、とウインクした。
あずさも緊張が解けたのか、柔らかく微笑む。
伊織…。
貴音は窓の外を見て、今もどこかで己を悔いているであろう少女を憂いた。
「あずささん、今の二人のやり取りって、なんだかドラマのクライマックスみたいでしたよね?! すごかったー! 演技賞ものでしたよね! なんだか二人ともかっこよかった?!」
小鳥が堪らない、とはしゃいであずさに耳打ちする。
「…音無さん」
「え?」
「…それ、今の二人に聞こえたら、多分、ひっぱたかれますよ。拳で」
あずさの顔は、微笑んではいるが目が笑ってない。
小鳥は蒼白になり両手で口をつぐんだ。
「お、お仕事してます」
「そうしてください」
口を押さえたまま、隠れるようにして机に戻る小鳥。
それから暫く、事務所に会話はなかった。
「私がアイドルになりたいなーって思ったのは、前にも話しましたけど、みんなが私の歌や踊りで元気になってくれたら嬉しいな?って思ったからなんです。まぁ、それ以外にも、私がバイトして家計の足しにっていうのも確かにあるんですけど…。えへへ」
やよいが765プロに応募しようとしたきっかけを話している。
「うん、そうだったわね。あんたも大変よね。兄弟も多いし」
「えへ。なんだか平凡な理由ですよねー」
「でも、それってとっても素敵な事だわ。少なくとも、自分の為にとかっていう理由よりはずっと…」
「い、伊織ちゃん! 伊織ちゃんは、えっと…そんなこと…あー…」
やよいが言いあぐねている。
「いいのよ。そう言えばあんたみたいに、はっきりとみんなにアイドルになりたい理由を言ったこと、無かったわね」
「あ! やっぱりそうですよね! よかったー! 伊織ちゃんが言ってくれたなら、忘れるはず無いのに、出てこなくってどうしようって思ってたんです!」
どかっと不安が落ちた顔で胸をなで下ろしている。
ほんと、やよいって分かり易いわよね。
うらやましい。
私みたいに、歪みのない性格が。
「で、一体どんな理由なんですか? 教えて下さい! きっと私が一番目ですよね!」
キラキラした瞳で迫るけど…。
「あー。えっと、二番」
ごめんね、やよい。
「えー!? 理由を聞いたのは、私が一番じゃないんですかぁ?」
がーん、っていう文字が見えそうなくらいにショックな顔。
猫の瞳みたいにって、こういうのを言うのかしらね。
「じ、じゃあ、一番は誰なんですか? 私よりも仲良しさんがいるなんてぇ…。うう…。なんだか、なんでか分からないけど、なんだかショックです…」
よよよ、と横座りで仰け反るやよい。
「あー、別に順位付けとかそんなんじゃないのよ。たまたま先に話す機会があって、そんな雰囲気だから言っただけなの。ね? やよいが二番とかそう言う意味じゃないから。私の友達一番は…えーと、なんていうか…」
「……」
やよいが次の言葉を待って、じっと私を見つめている。
ちょ、ちょっと、ますます言いにくいじゃない。
「…だ、だから…その…目の前じゃ言いにくいのよ…」
「! って言うことは! 私ですか? 私でいいんですよね!?」
「…やよいが、そう思ってくれるなら」
「思いまーす! わたし! 思ってます! そうなったらいいって思ってました! わぁーい! 相思相愛っていうやつですー!」
やよいが、がばっと抱きついてきた。
「そ、相思相愛はちょっとちがうでしょ!」
「あ、そうですか?」
「ま、まぁ、とにかくやよいの事、変な意味じゃなくって好きよ。それは本当」
「えへへ?。嬉しいです?」
やよいはすりすりとほっぺを寄せる。
うーん…。ここの事務所って、やっぱりなんだか、ちょっと…女の子同士のスキンシップが、ちょっと、ちょっとだけ、過剰な気がするわ。うん。
「で?」
「え?」
やよいがいきなり、すりすりを止めて真顔で聞いてきた。
「一番目って誰の事ですか?」
「…やっぱり、言うの?」
「言ってください」
「……」
「どうぞ」
マイクを持ったような手を私に向けるやよい。
「いいじゃない、そん」
「良くないです! このままじゃ、夜眠れません! ご飯おいしく食べられません!」
…なんでそんな事に拘るのかしら?
でも、真摯な瞳を見ていると無碍にも出来ないわ。
私は溜息をついて観念することにした。
「伊織の志望動機は、少々特殊と言えば特殊ですし、平凡と言えば平凡な動機でした」
765プロ、仮眠室。
灯りも付けず、未だベッドに座り込んでふさぎ込んだままの千早。
その側に貴音が座って語り始めていた。
「彼女は、自分に自信をつけたかったのです。自分が何なのか、何が出来るのか、何の為にいるのか、それに対して漠然とした不安を持っていました。貴女と同じです」
「…水瀬さんは、輝いていて…真っ直ぐで…。私なんかとは…」
ようやく顔を上げた千早が呟く。
「水瀬さんに、酷いことを言っちゃった…私…。私…」
「伊織も今頃悩んでいます。貴女と同じ様に、自分が相手を傷つけた、と。とても後悔しています」
「…そんな事…。どうして四条さんに…」
伊織は自分のような後ろ向きな人間の事なんか気にしない。そう、思っていた。
「分かります。私には、伊織の気持ちが。うぬぼれと思われても構いません。ですが、私が、一番伊織のことを理解しているのです。伊織と一番心が近しいのですから」
正にうぬぼれと言われても仕方ない言い振りだった。
だが、その言葉には自信があふれている。
いや、自信と言うよりも単純に確信していると言った方が正しい口ぶりだ。
「…どうしてそんなに自信が持てるんですか?」
「積み重ねです」
「積み重ねって…。水瀬さんと会って、まだろくに時間も経ってないのに」
「時間ではありません。心のやり取りの積み重ねです。自慢ではありませんが、わたくし、伊織とは貴女以上にいがみ合っていたのですよ。この短期間で」
千早は、はっとして、わずかに顔を上げた。
「初めて会った頃、わたくし、どうやら伊織に怖い印象を持たせていたらしく、まともに話をする事もありませんでした。わたくしも、正直最初は伊織の事を、あまり気にしていなかったのですが」
「それじゃ、関わり合いが無いじゃないですか」
うな垂れたままで千早が言う。
「そうですね。でも、実は伊織は違う、と知ったのです。コネに頼って、アイドルと言う照合を自分を飾り立てるステータス代わりにしようなどと考えているのではないと、そう知ったのです。如月千早、貴女は知りませんよね? 伊織があのやよい以上に、実は事務所の雑用を行っている事実を」
「えっ!?」
千早は今度こそ驚いて顔を上げた。
「前に、ふと予定の無い日だったのですが、お仕事の書類を見たくなって事務所へ行ったことがあります。その時、わたくしは伊織に会ったのです」
「お疲れ様です。小鳥嬢、宜しいですか?」
事務所の階段を上り、貴音は雑務をしていた小鳥へ語りかけた。
「あ、貴音ちゃん、お疲れ様。どうしたの? 今日は予定入ってないわよね?」
パソコンを見ていた小鳥がいらっしゃい、と微笑んで言う。
「ええ、近くまで来たものですから、それで、少々次回の仕事の内容を確認しておきたいと思いまして」
「熱心ね」
「と言うより、他の方がもう少し仕事に力を入れて然るべきかと思いますが」
事務所は結構人のいない日がある。
貴音はそれを憂いていた。
さらに正直な所を言えば、皆、アイドルと言う仕事に対して本気なのだろうか、とやや不信感を感じていたのだ。
「まぁ、それはそうかもね」
「小鳥嬢も、気をもんでいるのではないですか?」
「あはは、私は事務だから」
「今は、ですか?」
「ま、まぁそれはさておいて…」
「そうですね。まずはわたくしの用を済まさせていただきます。で、書類はどちらですか?」
「それなら、書庫の…」
そこまで言いかけ、小鳥がはっと息を呑んだ。
「あ! あのね、貴音ちゃん! 書類、私が取ってくるわ。貴音ちゃんはソファに座ってて!」
大慌てで席を立ち、書庫へ向かおうとする小鳥。
だが。
「自分の事で小鳥嬢の手を煩わせるような真似はできません。書庫ですね。了解しました」
貴音はそのまま書籍や書類をまとめて置いてある書庫へ向かおうとする。
「ま、待って! ほら、私事務だし! 私が…」
「わたくしの事は、わたくしでやらせて頂きます」
小鳥の制止も間に合わず、貴音は書庫の扉を開けた。
「ひゃっ!?」
「!」
小さな悲鳴が聞こえた。
貴音も思わず身をすくめる。
「…だ、誰? え? た、貴音!?」
「水瀬伊織?」
そこにいたのは、ジャージ姿の伊織だった。
慌てて後ろに何かを隠し、距離を取ろうとしている。
「何をしているのですか?」
「な、何でも」
そう言って伊織は目を泳がせた。
「何か物色でも?」
「そ! そんな訳無いでしょ! この私がなんでそんな事するのよ!」
だが、伊織は極めて不審な動きで貴音から距離を置こうと、じりじりと身を後ろへ下げ続ける。
よく見ればジャージは所々ほこりがつき、机の上にはまだ多数とは言えない仕事上の書類が整頓され、並べられていた。
「水瀬伊織」
「…なによ」
「滑稽ですよ」
伊織は目を見開き、息を呑んだ。
七へ Top 九へ

