
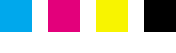

Idolm@ster 小説『歌姫咲く花の園』
六
結局、混乱した頭のまま次の日になり、なし崩しでレッスンが始まった。
それでも。
「千早。頑張りましょ。今までで一番大きなステージよ」
「ええ」
いろいろもやもやはあるけど、こんなところで立ち止まってなんかいられない。
まずは決心の握手。それと気合いのかけ声。
前を向いて進みさえすれば、きっと…。
この時はまだ、もしかしたら大丈夫だと思っていたと思う。
ううん、思いたかった。
だから、私は自分から握手したり、色々話しかけたりした。
でも…。
でも、おそらく私は分かっていた。この件がどうなるのか。
…もしかしたら、千早も。
そして、既にこの頃からだったのかもしれない。
みんなで別々に、いろいろな事が動き始めていたのは。
すごく、当然の事なんだけど…。
レッスンが始まって既に三週間。
本番までもう一瞬間を切っている。
なのに、私達の関係、練習内容は最悪の最悪だった。
「…なんだか、こう、何て言うか、しあいと読んで死合いと書く、みたいな雰囲気さー」
その日、私と千早のレッスンに、やよい、響、春香、貴音も来ていた。
レッスンを初めて二週間後、おじさまからの提案で、最後の歌の時に他の子達も登場させて、最後はみんなで歌って踊ろう、という事になった。
私は賛成。
最後にみんなで歌う。
素敵だと思ったわ。
そして、色々みんなで考えて、さっきの四人と最後にみんなで歌う事になった。
でも、その四人と合わせた練習が、話が決まって一週間経ったのに、実はまだ一回もまともに出来ていない。
理由は…理由は…その時は、千早のせいだと思っていた。
…最低よね、私。
「水瀬さん、ここのトーンはフラットに行くべきでしょう?」
千早が何度目か分からない駄目出しを繰り返す。
ああもう! 一回最後まで歌わせなさいよ!
「いいえ! 感情を表すのなら少し高くした方がいいのよ! ここは喜びを体中で表すところじゃない!」
そうとうイライラしていた私は、普段以上に声が高くなっていた。
周りのみんなも一触即発の険悪な雰囲気に引いているみたい。
仕方ないじゃない、本番はもう四日後なのに、千早が止めまくるから全然通しが進まないのよ!?
「でもそれじゃ歌が伝わらない! 譜面とちぐはぐになってしまうわ! 感情はいいけど、もっと正確に歌って!」
冷静だけど熱を帯びた千早の声。
正論は正論だけど、この極端な融通の利かなさが流石にうっとおしい。
「正確正確って、あんた、CDで聞く音楽じゃないのよ! その場で生で聞かせる歌なのよ! バンドだって生なのにそんな正確に出来る訳ないでしょ! どこの世界にライブ途中でちょっと音がずれたからって歌い直す歌手がいるのよ!」
「だからこそ少しでも正確に近づけるようにレッスンをするんでしょ! 聞きに来てくれるお客さんの為にも、いい加減な歌は聞かせられない!」
千早の言葉も熱を帯びているのが分かる。
冷静な千早が感情を剥き出しにしている。
それ自体はいいんだけど。
「いい加減って何よ! 私が音痴だとでも言う気!?」
「そんな事は言ってないわ! ただ、水瀬さんの歌には指定のキーを時々無視するきらいがあるから、そこを押さえて正しいキーで正確に、少しでも完璧に近く…」
必死に訴える千早の表情。
でも、千早の必死さが今は只の我が儘にしか聞こえない。
さっきだって、やっと最後のサビまでいったのにいきなりCD止めたのよ。
しかも理由がすごい。何かが違う、ですって。何かって何よ何かって!
「ああもう! あんたロボットか何かな訳? 本番じゃダンスも入るしこの曲の前にも何曲も歌うのよ! 休憩無しのぶっ続け! しかもスポットライトであっつくなってる! ステージだって見たでしょ? 思ったより古くて、ギシギシの滑りやすい、良くない環境よ! そんなところでキーの一つ一つを寸分の狂い無く歌えるってんならあんたが完璧にやりなさいよ! 出来るのよね!? 完璧な千早さん!」
「で、出来る訳じゃ…。だ、だからこうして、少しでも完璧になるように…」
完璧完璧完璧!
さっきからそればっかり!
私だって完璧にやりたいわよ!
でも、その前に通しをしたいの!
またあの子が私を見に来てくれるって手紙が来ていたのよ。
それなのに、このままじゃ最後までちゃんと出来るかが分からないじゃない!
みんなで考えた最後の歌の振り付け、まだ何にもやってないのよ!?
あと一週間なのよ!?
「レッスンでやっている今だってこんななのに、本番で今以上になれる訳ないじゃない! 実際にどれくらい疲れるのか、私は通しでやりたいのに! あんたがぐちぐち口挟むから半分も進めない! あんた、もしかして失敗させたいの?」
「そ、そんな訳…!」
「もういーかげんにして! 高い目標掲げるだけなら子供にだって出来るわよ! 私は見る人に楽しんで貰いたい! 自分も楽しく歌いたい! あんた、一体誰の為に、何の為に歌ってんのよ!」
千早がびくりと身を強ばらせた。
「だ、誰って…。私だって…。でも、まだまだプロと言うにはおこがましいから…だから、私は…かんぺ…」
またあの言葉を言いかけて口をつぐむ。
ここに来て弱くなった千早の態度にますますイライラしてきた。
ああもう!
いっそ逆ギレでも何でもいいから怒鳴るくらいしなさいよ!
反論しなさいよ!
私の方が、段々自分が押さえられなくなっているわ!
「私だって全然プロじゃないわよ! でも、歌うからにはプロと思って歌う! 仮にも人前で歌うなら、その場の状況に、本番の状況に合わせて歌うのがプロってもんでしょ! あんたの歌はプロとしてじゃなくて、自己満足を満たしたいだけよ! スタッフ困ってるのよ? 時間押してんのよ! 通しまだ一回もしてないのよ! 出来ない完璧にかじりつきたいのなら、ステージの上じゃなくて一人でカラオケでも路上ライブでもやって、死ぬまで完璧に拘ってなさい! お客を無視して! 自分の為だけに!」
千早がびくりと身を縮め、目を丸める。
それでも私の言葉は止まらない。
言いたくないのに、言いたくない事まで言い始めている。
自分で自分が押さえられない。
伊織、やめて!
私、これ以上言うと…!
「アイドルを軽く見ているのは、あ…」
突然声が遮られ、かわいた音が響いた。
視界が一瞬白く染まり、頬に、刺すような痛みが響く。
呼吸が止まった。
心臓すら一瞬止まった気がする。
たった今まであれだけ騒がしかったスタジオが、水を打ったように静まりかえっていた。
「伊織」
意識が飛んでいたんじゃないかと思うくらい何も聞こえなかった耳に、かろうじて私を呼ぶ声が届いた。
その声は貴音。
「伊織、それ以上言うのなら、あなたを軽蔑します」
私の心臓が破裂しそうに高鳴っている。
呆然として声のした方を見ると、右手を上げたままの貴音が私を真っ直ぐに見据えていた。
「……」
貴音が怖かった。
私は腰が抜け、その場にへたりこむ。
貴音の目が怖いのに、目を背ける事が出来ない。
もっと叱られるような気がして。
何か言いたい訳でもないのに私は口を魚みたいにぱくぱくさせる。
それから、次第に体の震えが大きくなっていくのが分かった。
頬の痛みは今頃になってじんじんと痛さと熱さを増し、しゃっくりみたいに息をする度に両目から涙がぼろぼろと零れだした。
じっと私を見詰める貴音の目が恐い。
どうしようもなく怖い。
恥ずかしい。
私は大きな嗚咽を漏らしながらよろよろと立ち上がり、そのままスタジオを飛び出した。
何度か壁にぶつかったみたいだけど、痛みなんて感じなかった。
きっとものすごく情けない格好だったんだろうな。
でも、恥ずかしいなんて感じる余裕は無い。
私はとにかく、何でもいいから、ここ以外の場所に逃げたかった。
いっそ消えてしまいたかった。
伊織が飛び出した後のスタジオ。
誰も動かず、誰も喋らない。
「……」
貴音が、伊織をぶった右手をじっと見詰めている。
その瞳は、まるで自分がぶたれたかのように沈痛な色に染まっていた。
千早はしゃがみ込み、顔を埋めて動かない。
「あの…千早さん…」
春香が恐る恐る近づき、隣にそっとしゃがむ。
「また…」
蚊の鳴くような声で千早が呟いた。
「え?」
「また、やっちゃった…」
「千早さん?」
顔を埋めた膝の間から、床にぽたぽたと涙が零れていた。
「水瀬さんの言う通り…。私、自分が出来ない事を棚に上げて、あら探しばかりして…」
千早は体を丸めてますます小さくなる。
「歌を、誰の為に歌うのか…私は…」
声が震え、言葉が良く聞き取れない。
その震えが千早の悲しみ、戸惑いをそのまま表現していた。
「千早さん…」
隠さぬ悲しみ。
否、とうてい隠せぬ、深い悲しみ。
それを感じた春香が自分も瞳を潤ませ、そっと肩に手を置く。
「私…どうして…」
抑えていた嗚咽がだんだん大きくなっていった。
「ち、千早さん…あの…」
「…すい…ません…今は…ごめんなさい…」
嗚咽に混じる静かな拒絶。
春香は何も言えず、そっと立ち上がる。
その時、先程よりもずっと大きな、乾いた音がスタジオに響いた。
「きゃっ!?」
「ひゃっ!?」
同時にやよいと響の声も。
「え!?」
春香が振り向く。
それは、貴音が自分の頬を自分でおもいきり叩いた音だった。
叩くと言うより殴るに近かったかもしれない。
それくらいに大きな、重い音。
「た、貴音さん?」
思わぬ行動におろおろするばかりのやよいと響を尻目に、春香が問いかける。
「…伊織の痛みは、こんなものではありません」
どれのどの勢いで叩いたのか、みるみる頬が痛々しい紅色に染まる。
「貴音さん…」
「わたくし、伊織に、酷い事をしました。でも、伊織にあれ以上汚れて欲しくなかった…。伊織に、あれ以上愚かになって欲しくなかったのです…」
赤くなった頬もそのままに、俯きながら絞るような声で言う。
唇をかみしめ、握った拳は白くなっている。
貴音は伊織の事を毛頭蔑んでもいないし、憎いとも思っていない。
少なくとも、今ここにいる誰よりも伊織を心配していた。
だからこそ、自分の身を挺して、自ら進んで悪人となり、伊織を止めたのだ。
春香は、小さくはい、と頷く。
春香もそう思っていた。
誰が悪いとも思っていない。
ただ、想いの違いがかみ合わなかっただけなのだ。
「…あ、あの…あの…」
今にも泣きそうな声が聞こえる。
春香が振り向くと、実際目に涙を溜めたやよいが、恐る恐る、小さく挙手していた。
「あ、何? やよいちゃん」
春香は、迷子に問いかけるみたいに目線を合わせた。
「あ、あの…い、伊織ちゃんを…捜してきても…いいですか? 伊織ちゃん、きっと今…な、泣いて…あの、私…」
やよいの声にも嗚咽が混じり始める。
「いお…伊織ちゃんは、わ、悪い子なんかじゃ…ないんです…ほん…本当です…伊織ちゃん…伊織ちゃんは…」
やよいもまた伊織の事を心底心配していた。ひいきでも何でもない、心の底からの憂慮。
「い、行ってきて…いいですか?」
「あ、じ、自分も…!」
響も言いかけたが。
「響ちゃん、ここはやよいちゃんに任せましょう。大勢で行っても、伊織ちゃんが逆に困っちゃうと思うの」
春香がそっと制止する。
「あ、そ、そうかな? ん…それじゃ、仕方ないさ。やよい、あのさ、伊織のこと、お願いな?」
響はやよいによろしくな、と告げた。
「はい。行ってきます!」
よほど追いかけたかったらしい。
やよいはばねで弾いたように飛び出して、行きかけ、はっと立ち止まる。
「あの、千早さん…伊織ちゃんの事…許してあげて下さい」
やよいはぶん、とおじぎして、今度こそ外に飛び出す。
スタジオはまた暫く静かになった。
少しして、貴音が動き出す。
「…千早、あなたもまずは落ちつく事です」
貴音が囁くように言って、肩に手を置いた。
千早は体をびくりと強ばらせたが、直ぐに脱力し、はい、と弱々しく返答をする。
ふらふらと立ち上がると、涙でぐしゃぐしゃになった顔のまま幽霊みたいな足取りでスタジオの隅の椅子に座り、そこで再び膝を抱えてうずくまってしまった。
「だ、大丈夫かな…」
響が心配そうに言う。
「少し、時間をあげましょう。響ちゃん、悪いんだけど、これでみんなの飲み物買ってきてくれるかな?」
春香が小銭入れを渡すと、響は分かったさー、と快く引き受けてスタジオを後にする。
「…どうしよう」
春香がこの状態をどうしたものか、と思い悩む。
スタジオの空気は重い。
「春香さん、わたくしが事務所に連絡します」
貴音が言う。
「あ…そうですね。これは一応報告しておいた方がいいですよね…」
「春香ぁ」
そこへ響が帰ってくる。
「お帰りなさい。ごめんね、重かったでしょ」
と、響を見るが手ぶらだ。
「あれ? 響ちゃん、ジュースは?」
春香が問う。
「…あのさ、春香」
響が言いにくそうにしながら小銭入れを差し出す。
「ん? どうしたの? 何でもいいのよ?」
「いや…えっと、十三円じゃ、ちょっと…」
「え?」
まさか、と大慌てで小銭入れを受け取り中を見る。
「…あ」
響の苦笑いと同時に春香が顔を真っ赤にして慌てた。
「わあぁっ! ごごごごめんなさい! ま、間違いよ! ただの間違い! わ、私が行ってきます!」
春香はバッグから財布を鷲掴みで取り出すと、逃げるようにして外に出た。
「…ちょっと、和んださー」
響は苦笑いして春香を見送った。
「伊織ちゃん! 伊織ちゃーん!」
やよいが走っていた。
オフィス街だが今の時間出歩く人は少なく、慣れていない道のせいもあり、ゴーストタウンに迷い込んだような錯覚すら感じる。
人の気配はするのに、姿は見えない。
そんな不安定な街の雰囲気に、このまま伊織が消えていなくなってしまう様な、そんな漠然とした不安が重なり、やよいは足を早めた。
「伊織ちゃーん! どこですかーっ!」
少しの後、やよいはふと予感を感じ、雑居ビルの裏手に回る。
そこは雑然としたゴミ集積所。
普通なら絶対に立ち寄らないような場所だが、やよいは胸騒ぎを覚えて足を踏み入れた。
「…伊織ちゃん? います…か?」
どことなく大きな声を出してはいけないような雰囲気に、やよいは声を潜める。
「…!」
ふと、非常階段下の暗がりで何かが動いた。
「い、伊織ちゃん?」
恐る恐る近づく。
「伊織ちゃん!」
やよいは声を上げた。
そこには、ジャージを汚してゴミの一部のようになってうずくまる伊織がいた。
「……」
声に反応して伊織が頭を上げた。
その目は泣きはらして真っ赤だ。
いや、今も瞬きする度に涙がぽろぽろとこぼれ続けている。
「…やよい…」
やよいの存在に気付いた伊織は、泣き止むどころかますます大粒の涙を零し、そして声を上げて泣き始めた。
やよいが駆け寄ると、必死にその腕にすがって更に泣き出す。
まるで、まだ目の見えぬ赤ん坊のように。
「…千早さんは?」
スタジオ。
春香が貴音に問う。
ジュースを買って戻ってくると、千早の姿が無かった。
「事務所に戻りました。不安だったので、タクシーを呼びました。着きそおうかとも言ったのですが、独りでいい、と」
貴音が静かに答える。
「…今日は、もう帰ってもいいと思うんですけど…」
「それも言いました。ですが、こんな時に、家にだけは帰りたくない、と」
窓の外を見ながら、貴音が言う。その瞳には伊織に向けたものとはまた違う切なさが宿っている。
「…家にだけは?」
「詮索はしておりませんが…」
「千早の家ってさ、あんまり両親仲が良くないみたいさ」
響がドクターペッパーを飲みながらぼそりと呟く。
「あ、別に探ったんじゃないさ! ただ、事務所で、携帯で千早がそう言う事話しているの、偶然耳にした事があって…」
「…やっぱり、そうなのかな」
春香が呟く。
「え? 春香、知ってた?」
「私も、小鳥さんにちょっとだけだけど。小鳥さん、だから、前にこう言った事があるの。変に意識する必要は無いけど、あんまり両親関係の話題は振らないでって」
「そっか」
響が天井を見上げた。
「…いろいろ、あるさー」
「成る程、分かった」
高木が電話を置いた。
「どうしました? そんな難しい顔をして」
丁度お茶を持って来ていた小鳥が問いかける。
「いや、ちょっとね。千早君がこれから戻ってくる」
「あら、早いですね。それじゃお茶の準備…」
「しばらく、そっとしておいてくれたまえ」
高木は待ちたまえ、と手をそっと挙げる。
「…何か、問題でも?」
普段より神妙な面持ちの高木の顔を見て、小鳥も何かあった、と気付く。
「…これから、問題になるかどうか、だね」
「…?」
小鳥はお盆を抱えて首をかしげた。
「千早君の件も今後考えなければならないが…。律子君も、あの子に、なかなか厳しい試練をぶつけてくるものだ」
高木は椅子に深々と座り、天井を仰ぐ。
「小鳥君」
「はい」
「…今日の、いや、明日一日を見て、何らかの問題が残ると判断した場合、コンサートのメンバーを、再考する」
「…はい」
小鳥の顔もいよいよ神妙なものとなる。
「…正念場だ。二人とも」
高木は、互いにどこか違う場所で泣いているであろう少女達の顔を思い浮かべながら、そっとエールを送った。
五へ Top 七へ

