
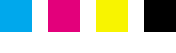

Idolm@ster 小説『歌姫咲く花の園』
五
「今日はありがとうございましたー!」
最後の曲が終わった!
あいにく、時間の関係でアンコールは無しだけど、殆どの人がずっとライブを見続けてくれていた。
私は、私を見てくれている人達の為、自分の出せる力を出し切り、もう喉がかれる寸前まで気張って歌い続けた。
帰り際、最後まで見ていてくれた男の子に振り返って、もう一度ウィンク。
男の子はそれに気付いてくれて、ことさら大きな拍手と満面の笑みで見送ってくれた。
拍手と歓声が最高の栄養剤。
袖に消えていく途中から、既に元気がわき上がってくる気がしていた。
「伊織ちゃん! お疲れ様ですー! すっっっごく良かったですよ! 感動です〜!」
やよいがスポーツドリンクを手に迎えてくれた。
「ありがとう、やよい。…みんなの、おかげだわ」
「えへへ、伊織ちゃん、なんだかカッコイイです」
「ふふ。そりゃそうよ。765プロをしょって立つ、水瀬伊織ちゃんのステージなんだからね」
今日はいい夢が見られそうだわ。
私は意気揚々と事務所へ戻る。
そこには、みんなが私を賞賛の目で迎えて…くれる程甘くはないのよね、これが。
ちょーっとは期待したんだけど。
ちょーっと、ね。
「やっぱり曲の順番を少し変えるべきだったと思いますね。ちょっと前の方にアップテンポの曲が集中してます」
律子がプログラムを見なおしながら言う。…やっぱり前半盛り上げようとしすぎた?
それにしてもいつもながら的確だわ、律子は。うん。
「後半はちょっと疲れていたようですから、もう少し静かな歌を多く選ぶべきだったと思います」
千早がビデオとにらめっこしながら言う。はいはい、分かってるわよ。
「でも、一生懸命が伝わって良かったと思うの。おでこもキラキラだったの」
美希、ありがと。て言うかおでこは関係ないわ。
「伊織には、もう少しダンスレッスンは必要ですね。足下が少し危うかったようです」
これは貴音。…思い当たる節があるから反論出来ないわ。足、ちょっと痛いしね。
「そう言えば、ソックスが片方裏返しだったみたいですね〜。白だから目立ちませんでしたけど」
げ。あずさ、あんたちゃらんぽらんに見えて確認が鋭いわね。
「では、みなさんの意見は、まぁこんなところでしょうか。伊織ちゃん、あなたからは何かある?」
「…これ以上駄目出ししなきゃいけないの?」
事務所のロビー。
ローテーブルを囲んで座れる人は座り、他の子は立ちながら、今日のライブの反省会が続いていた。
他の子の時は、丁度その場にいた子達だけでビデオを見て、同じ様な事をしていたらしい。
だから、今日の私の駄目出しが全員で行われるのは必然。
…大取の重要さがこれ程とは思わなかったわ。
私はうさちゃんに顔を埋めてソファーに沈むとため息をついた。
「初めてのステージで浮つくのは分かるけど、これが後々大切になるんだから、厳しくした方があんたの為だよ。最初が肝心。今日みたいにステージを大成功で終わらせたいならね」
律子が釘を刺す。
「分かっているわよ。でも、もーちょっと褒めて欲しいわ」
せっかくの楽しい余韻が今はもうぼろぼろよ。ホント。
「褒めてくれるのはお客さんのお仕事。私達のお仕事は、アイドルを目指すみんなを、互いに叱咤激励しあって、高めあっていく事よ。そのご褒美が、ステージで味わえるファンの歓声なんだから。ね?」
律子が私のおでこをちょん、とつつく。
「はーい。そうね…んーと、やっぱり、もうちょっと肺活量って言うか、体力は必要かしら? 三曲目でちょっと息切れしていたもんね。水泳でもしようかしら?」
「いいわね。体力はアイドルでも何でも、最も必要な基礎だから」
小鳥がメモしながら言う。
「まぁ、今日はこれくらいにしておこう。伊織君、改めて、ご苦労だったね」
そこへ、奥の机に座ってみんなのやりとりを聞いていたおじさまが立ち上がり、にっこりと微笑んで言ってくれた。
「はい、ありがとうございます!」
ステージが始まる前のおじさまの言葉を思いだし、私はおじさまの言葉でようやく本当にステージが終わった気がした。
「さ、みんな、おまたせ。打ち上げの始まりよ!」
そう言って小鳥とあずさが給湯室からオードブルと飲み物を持ってきた。
デリバリーとかによくあるヤツだけど、こういう時の食べ物って雰囲気だもんね。
見ていなさい。
そのうち、専属シェフを置いてこの場で調理した料理を出せるようになるまでになってみせるわ。
伊織ちゃんの野望はまだまだなんだから!
みんながテーブルの周りに立ち、その手にはジュースやらお茶やらが持たれている。
揃ったところでおじさまが一つ咳払いした。
「今日のライブはお世辞ではなく素晴らしいものだった。無論、今までのみんなのライブもそうだ。今日、会場に足を運んでくれたテレビ局、雑誌社関係の人達の感触も悪くなかった。みんなのライブのDVDもちゃんと渡しておいたから、これから先オーディションを受ける時にもきっとプラスの要素になるだろう。みんな、今日はご苦労だった! では、話はこれくらいにして、765プロの未来の為に、乾杯!」
「かんぱーい!」
みんなの声が一つになって響いた。
うん、悪くないわね。
こういうの、『団結』って感じだわ。
初めてのステージが終わったその日の夜。
私はパパに報告した。
正直、おっかなびっくりだったけど、パパはとっても喜んでくれた。
但し、これからが大変だぞ、と釘はしっかり刺されたけど。
はい、分かりました。
私は感謝を込めて、パパにぎゅーってした。
「宜しゅうございましたね。お嬢様」
部屋を出ると、新堂が廊下で待っていた。
あんたもありがとう。
「ええ、新堂にはこれからも色々お世話になるわ。よろしくね」
「はい。お嬢様の為でしたら、この新堂、例え地雷原だろうが、血吸いヒルが飛び交うジャングルだろうが、どこへでもお嬢様を送り迎え致しますぞ!」
いや、頼まれても行かないから。
「おはよー」
数日後。
私が事務所に出ると、社長室で律子がおじさまとなにやら話し込んでいた。
「どしたの?」
「ん、お仕事の話よ。熱心よね、りっちゃんは」
小鳥が感心感心、と頷く。
ホントね。ああしているとアイドル候補って言うよりプロデューサーみたいだわ。
…これも、その時はまさかそう来るとは思ってもいなかったのよね。
「伊織ちゃん、お茶でも飲む?」
「いいわね。頂くわ」
小鳥は冷たい紅茶を煎れてくれた。
ん、ミントを浮かべるあたり、あんたも分かってきたわね。
「そうだ、もうすぐ一時よね。伊織ちゃんってお昼食べた?」
「んー、まだよ。この前行ったパパの知り合いのお店はどう? また新堂に連れて行ってもらえばいいわ」
「あはは…。あ、あそこは確かに味も雰囲気も最高なんだけど…。お財布が軽くなるから、もうちょっとお手柔らかなものはないかしら?」
小鳥があそこは勘弁して、お願い、と首をかしげて言う。
あら、そうかしら? 知り合い価格になっている筈だけど。
「では、ラーメンなどいかがですか?」
「ひゃわっ!?」
背後から突然声がする。
振り向くと、そこには貴音が立っていた。
「…い、いつの間に?」
「たった今です。ダンスレッスンの帰りですわ」
見ると、バッグを抱えていた。
ああ、なる程。
「だ、だからどうして音もなく後ろに立つのよあんたは!」
「騒がしいのは好みませんので」
そう言ってソファの後から回り込み、私の隣に座る貴音。
「…適度ってもんがあるわよ適度ってもんが」
「気をつけます。あ、これ少しいただいていいですか?」
貴音は飲みかけの紅茶をみつけて聞いてきた。
「いいけど…新しいの煎れてもらえば?」
「あ、貴音ちゃん、出すわよ?」
「いえ、これがいいです。では」
そう言って貴音は私が飲んでいた紅茶のストローに口を付ける。
「…落ちつきました」
「そ」
「ミントとほんのりした甘みがいいですね」
あれ? これ砂糖入ってないけど…?
ま、別にいいわ。良く分からないけど気分的なものなんでしょ。
「今日は千早と一緒のレッスンでした」
あ、そ。
「……」
貴音が私の顔をのぞき込む。
「な、何?」
「伊織、感情にかまけるのは感心しませんよ」
「な、何の話よ!?」
「分かっている筈ですよね」
「…う」
私は逃げるみたいに向こうを向いて、うさちゃんを強く抱きしめた。
…どうしてだろう。変に何かあった訳じゃ無いのに、なんだか、千早の事を、私…。
「……」
何も言えないでいると、突然貴音が私の頭を撫でてきた。
「ちょ、ちょっと!」
「いえ、何となく」
「やめてよ! 子供扱いは!」
心の中を見透かされた気がして、思わず大きな声を出してしまう。
ああ、自分のこういう癇癪みたいなところも本当に直さないと駄目だわ。
「決して子供扱いからではないのですが」
「何でもいいから、勝手に頭撫でないで。…いけないって分かってはいるつもりだから」
「ええ。善処します」
いや、善処じゃなくってやめて欲しいんだけど。
「で、どうしますか?」
「え?」
「ラーメンです。この近くになかなか侮れない味のお店がありますよ」
貴音は話題を切り替えてくれた。
ラーメン、本気だったんだ。
私はちょっと意外だった。
貴音の素性に詳しい訳じゃないけど、なんとなく私に似ている雰囲気を感じているのよね。
きっとどこかのお嬢様なんだと思うんだけど…。
だから、ラーメン屋って単語は意外だわ。
「わたくし、麺類は結構たしなむのです。最近の新規のお店は、残念ながら大抵スープも麺も、繰り返して食す気になれない目新しさばかりが目立つお店ばかりで、馴染みにしたい対象外ばかりなのが悲しいのですが、古くからのお店には、何年でも何回でも食べたくなる確かな味がそこかしこに隠れているものなのです。尖らぬ旨味とそれを包み込んで離さない麺、この基本が一番大事なポイントですね。やはり、レシピや分量だけでは計れない長年の勘、というものが真似の出来ない味を生み出すのでしょう」
「……」
びっくり。
貴音がこんなに熱心にラーメンを語るなんて。
しかも言い方が上手いからなんか食べたくなって来ちゃったわ。
「…そうね、試してみるのもいいわ。小鳥は?」
「あ、私は勿論オッケーよ! 貴音ちゃんが捜してくるお店って本当に美味しいお店ばっかりなんだから!」
あ、知ってたんだ。
「他のみんなも知っていたの?」
「全員ではありません。小鳥さん以外は特には」
小鳥は貴音をみて、ねー? と子供が内緒を共有したみたいな悪戯な微笑みを浮かべる。
あんたら仲いいわね。
「…ふーん。私が一緒に行っていいの?」
「伊織と食べに行きたいと思ったのです」
「そ、そうなの?」
そ、そんな真っ直ぐに見られても困るわ。なんか変な気分になるじゃない。
「では、行きましょう」
「はーい。伊織ちゃん、ちょっと事務所閉めるから先に出てね」
小鳥は上着を持って靴を外履きに履き替え始めた。
「あれ? 社長と律子は?」
「とっくに出たわよ」
「え? 気付かなかった」
あれ? 私、そんなに話し込んでいた?
「わたくしと入れ違いでした」
「そだったんだ」
何の話してたのかしらね?
「今日はこの後夕方まで出る予定の書き込み無いわね。女三人、ちょっとのんびりしましょ」
小鳥はにっこりと微笑んで上着を羽織った。
「へぇ、思ったよりお店多いのね」
事務所を後にして十五分くらい歩いた。
考えてみると事務所の周りをこんなにゆっくりと歩いた事なんて無いから、知らない道やお店ばかり。
意外に面白いわね、この辺り。
て言うか、貴音と散歩自体が初めてじゃない。
「私は?」
小鳥がのぞき込む。
「ちゃんとカウントしているから安心なさい」
小鳥は良かった、と笑う。
あんた時々可愛いわね。
「あ、伊織ちゃん見て。ここのアクセサリー屋さん、伊織ちゃんと同年代の子に人気のお店なのよ。安い割に人造石とかじゃない天然石が多いの。まぁ、加工し易さやデザイン的に模造石とかも普通にあるけど」
「あんた詳しいわね。年代違うお店なのに」
「ね、年代が違っても入って悪いわけじゃないもん!」
小鳥はぷぅ、とふくれる。
訂正。あんた可愛いんじゃなくて幼いんだわ。
「伊織、こちらはわたくしがひいきにしている雑貨店です。品のいいピューターが多いし、時々アンティークも入荷するのがいいところですね」
貴音はちょっと通りから奥まったところにある雑貨屋を教えてくれた。
ふぅん、普通のビルのペナントだけど、入り口から壁から、木造風にしているのね。シックな感じがいいわ。
そんな感じでいくつがお店を見て回った後。
「はい! 伊織ちゃん! ここが例のラーメン屋さんよ!」
「…ここ?」
そこは、見た目的には、どうにも褒められた作りじゃない小さなラーメン屋だった。
「あんた、よく最初にこんなお店に入ろうと思ったわね」
「藁苞に黄金、と言う言葉もあります。わたくしは、この暖簾の古さに心を引かれたのです」
そう言って貴音はそっとお店の暖簾に手を寄せた。
ああ、確かにこれは年季の入っている暖簾だわ。
えーと…大正五年創業!?
何このお店、百年近くやってるわけ?
「うわ…よく見つけたわねこんな古い所」
「味は保証しますよ」
貴音はいかにも馴染み、といった感じで暖簾をくぐる。
意外に様になっているのが不思議だわ。
「へいらっしゃい!」
中はカウンター十席とテーブル三つの小さなお店。
カウンターの中に、こういっちゃ失礼だけど干物みたいなおじいちゃんが立っていた。でも、その見た目の割に声がおっきい。
「全部載せお願いします」
「へい、いつものように二杯目は麺固めの卵二つのせで?」
「よしなに」
「……」
馴染み過ぎよ、あんた。て言うか二杯も食べるわけ?
「おじさん、こっちも全部載せお願いしまーす」
「へい! こちらもいつものように二杯目は麺少なめのチャーシュー倍ですね?」
「よしなにー」
あんたもかい!
「伊織はどうしますか?」
貴音が聞いてくる。
「えーと…ど、どういうの頼めばいいの?」
自慢じゃないけどこういうところ疎いのよ私。
馬鹿にしてるとかじゃなくて、単純に行く機会が無いから。
この前なんかやよいとおそば屋さんに行ったら、食券システムが最初分からなくて直接注文しようとしちゃって恥かいちゃった。
「でも、やよいちゃん嬉しそうに話していたわよ。伊織ちゃんが立ち食い蕎麦屋さんにつきあってくれて嬉しかったですーっ! って」
小鳥が笑う。
「別に、何所にだって付き合うわよ。漫画じゃないんだからお店を高級かそうでないかなんかで忌諱してないわ。本当に行く機会が無かっただけ。屋台だって行った事あるんだから」
「へ? 伊織ちゃん、ほんと?」
「それは面白そうですね」
あ、余計な事言ったかしら?
小鳥はともかく貴音、あんたも一緒に目を輝かせるのやめて。
「で、屋台とはどのような?」
…やっぱり言うのね。
「はいはい。私がまだ幼稚園くらいの頃よ。うちのパパとおじさまって、昔からの馴染みでしょ? 若い頃を思い出して、いわゆる赤提灯で時々お酒飲む時があるの」
「ああ、社長って繁華街の屋台とかくわしいものね。しょんべん横町とかで、よく潰れるまで飲み歩いたとか、楽しそうに時々話すもの」
「しょ…と、とにかくそういう話を私が聞いてて、すっごく楽しそうにしているパパを見て、どうしても一緒に行きたい行きたいってぐずったらしいの。覚えてないけど。で、仕方なしに連れて行ってくれたんだって」
「へぇ、幼稚園児にして赤提灯デビューしていたなんて、なかなかの強者ね」
「伊織の認識を改める必要がありますね」
「いや、あのね、あくまでも連れて行って貰っただけだから。しかもその後が語りぐさになるくらい傑作らしいの」
「ほうほう、どんなどんな?」
「パパとおじさまがいい感じに酔ってきたのを見てね、勿論私はジュースだけど、幼いながらもあの水に何かある、と思ったらしいの。でも、パパとおじさまは当然それを呑ませてはくれないでしょ? で、私、何を思ったのか知らないけど、急に酔っぱらった振りを始めたんだって。うぃーひっく、もっとさけもってこーい! みたいな感じで」
「あら」
「まぁ、可愛らしい。上手ですよ」
あ、いけない。思わず感情込めてやっちゃった。
「うふふ。伊織ちゃん、その頃から役者の素質あったんじゃない?」
「笑い事じゃないわ。その後よ。問題は。その場ではパパもおじさまも、他のお客も分かっているから問題無かったんだけど、私、悪のりしたのかその気になっていたのか、家に帰ってからも酔っぱらった振りを続けていたみたいなの」
「うふふ、か〜わいい」
小鳥がくすくすと笑う。
「聞きなさい。でね、それを見たママや新堂がね、パパが私に本当にお酒を飲ませたんじゃないかって疑っちゃったの」
「まぁ」
「で、私は酔った振りを続けちゃうし、しかも悪い事に服にお酒の臭いが移っちゃっていたから、これはいけないって、あとちょっとでお医者様を呼ぶところになっちゃたの」
「それは…なかなか問題になりますね」
「幸い、息がアルコール臭くなかったし、私も幼稚園児の演技だからおんなじ事繰り返しているってみんな気付いて、なんとか事なきを得たんだけど…」
「それは良かったわね」
「パパがその時ばかりはママや新堂に平謝りだったらしいわ」
「…とばっちり、とは言い切れないのが辛いですね」
「それ以来らしいわ。パパがぜ〜ったいに私をお酒が関係する席に連れて行ってくれなくなったのは。それにお正月の御神酒すらも、つい数年前まで舐める事もさせてくれなかったし」
「今は?」
「最近は流石に行事としてのお酒の関わりは許してくれるわよ。ま、どうせ神事の口つけ程度しか元々やらないけど」
「よっぽどその時の伊織ちゃんの演技が上手かったのかしらね?」
「ま、才能の片鱗は既にあったんじゃないの? 流石は私よね。にひひっ♪」
「ふふ。では、これからも期待します」
貴音が微笑む。
う。ま、まぁ見ていなさい。あんたにも私をちゃんと認めさせてみせるわ。
「認めているからこそ、期待するのですよ」
「わ、分かったわよ。あんまりそう言う事言わないで。なんだかむず痒くなるの!」
「謙虚ですね」
「だーかーら!」
「へいおまち!」
そこへラーメンがやってきた。
あら? 私頼んだ?
「初めての場合にお勧め出来るものを頼みました。勝手ですが」
「あら、そうだったの。ううん、いいわよ。ありがとう」
私の前に置かれたラーメンを見る。
うん、いい香り。
「ふぅん、醤油味ね。これって鶏肉?」
「実は烏骨鶏の肉です。スープもそうですよ」
「あら、烏骨鶏なんて珍しいわね。それじゃ、いただくわ」
私はスープを一口飲んでみる。
「へぇ、思ったよりコクがあるわね。でも、しつこくないわ。なんだか…すごい濃厚だけど、口に残らないのね。ふぅん」
私はもう一口のみ、そしてそのまま麺にも口をつける。
「……」
いつの間にかどんどん箸が進む。あ、これって確かに癖になるかも。
「気に入ってくれたみたいですね、伊織」
貴音がすごいボリュームの全部乗せを食べながら言う。
「あ、うん、なんかおいしいわ、これ。成る程…。確かにこれは癖になるわね。割と甘い気もするけど、それでいて醤油の風味もコクもしっかり出てる。出汁もいいわね、これ」
「連れてきた甲斐がありました」
「うん、伊織ちゃん、また一緒に来ましょ」
「そうね、今度は全部乗せ頼んでみようかしら?」
「うふふ。ラーメン部に一人会員が増えたわ」
小鳥が楽しそうに笑って言った。
私も自然に笑い返している。
ああ、こういう時間もいいものね。
思わず食べ過ぎた私。
その日の夜、体重計に乗るのがちょっと躊躇われたのは内緒。
伊織達が昼食を食べていた時刻。
別の場所のとある喫茶店。
開放的な一般の喫茶店と違い、席の一つ一つの間隔が広い、談話室的な喫茶店。
そこに、高木と律子が向かい合って座っていた。
「ふむ、やはり将来的には…その信念に変わりは無いようだね」
ウインナーコーヒーをすすりつつ高木は呟いた。
「はい、私、やっぱりそうしたいんです」
真剣な眼差しの律子が高木を見詰めて言った。
手元の紅茶のグラスに、大粒の水滴がまとわりついては滴り落ちてを繰り返していた。
「君の才能なら、まぁ大丈夫だろうし…。うむ、分かった。君の情熱は間違いなく本物だ。まぁ、暫くは今の状態を続けて、君の琴線に触れる人材が現れたと思ったら、まずは報告してくれたまえ」
「ありがとうございます。…実は、おおよそで目星はつけちゃったりしてるんですよね」
律子は悪戯っぽい笑みを返す。
「おいおい、まさかもう行動を始める来かね?」
「いえ、私自身が今は素人同然です。暫くは勉強を続けます。まぁ、ちょっとカマかけくらいはすると思いますが」
「それはいいが、行動の際は必ず報告と許可だけは忘れないでくれたまえ。同じ事務所内とは言え、これは大事な事だ。将来に関わるのだからね」
高木は社長の顔で言う。
「はい」
対して律子も真面目な表情で頷いた。
「つきましては社長、早速一つ、候補の子に試練をぶつけてみたいと思うんですが」
「いきなり試練かね?」
「あの子は…私が、一番賭けたいと思っている子ですから」
「ふむ、君に気に入られるというのは、それだけで大層な試練のようだね」
「大丈夫ですよ。あの子は。なんて言ったって、私のもう一つの人生を賭けるに値する、ダイヤの原石なんですから」
律子の微笑みは、信頼という名の自信に満ちていた。
「おはよー」
いつものように事務所に顔を出す。
「おはよう、伊織ちゃん。あら、今日の髪飾りはなんだかゴージャスね」
「にひひっ♪ よく見ているじゃない。髪飾りの薔薇の花びらに、水滴に見立てたダイヤをあしらったのよ」
「ダ、ダイヤ? そんなにいっぱい?」
小鳥が目を丸くする。
「そんなに驚かないで。実はイミテーションだから」
「あ、そ、そうなんだ。びっくりしちゃった」
「本物は自分で買えるようになってからよ。でも、すぐだと思うけど。なんたって私はダイヤの原石なんだから」
「うふふ、調子いいみたいね」
小鳥が楽しそうに微笑む。
さて、今日の予定はボイスレッスンとスイミングだったわね。
「あ、伊織ちゃん、その前にちょっといいかしら? 社長がお呼びなの」
「おじさまが?」
「うん。すぐ行ってもらえる?」
「分かった。すぐ行くわ」
と言っても、小鳥のデスクから社長室までは歩いて十秒かからないんだけどね。
「失礼します」
私はノックして社長室に入った。
「やぁ、伊織くん。調子はどうかね?」
「とってもいいですよ。昨日の新作アイスのキャンペーンもいい評価を頂きましたから」
そう、昨日私はとあるアイスメーカーの新作、ボリボリ君って名前のアイスのキャンペーンガールをやったの。名前のセンスはあれだけど、食べたら美味しかった。
それと律子がお供に来てくれたわ。
色々な指示がちょっとうるさくもあったけど、おかげでとっても好評。
解説中、うっかり科白忘れたところはアドリブ入れちゃったけど、その機転は褒めてくれた。
もっとも、そもそも科白を忘れないようにっておこごとも貰ったけど。
「うむ、報告は聞いている。ご苦労だったね。非常に好評だったようで、おかげでみんなに配ったのに、まだフリーザーがアイスでぱんぱんだよ。いやぁ、こんなに提供してくれるという話は無かった筈なのだが」
「あ」
「ん? 何かね?」
「いいえ。何でも」
…もしかして、昨日の打ち上げに来ていたメーカーの専務さんに冗談で言った「伊織、頑張ったご褒美に美味しいボリボリ君がた〜くさん欲しいなぁ。うふ♪」を本気にしちゃったかしら?
「さて、本題だが」
「あ、昨日の話じゃなかったんですね」
「うむ、きっと君にとっても魅力のある話だと思うよ。まずは座ってくれたまえ」
おじさまが話してくれた内容は、確かにすっごく魅力的なものだった。
おじさまは、ペアでステージをやらないかと提案してきたの。
しかも場所は駅中とかデパートじゃない。
ステージ。
ある街の劇場のちゃんとしたステージ。
最近、にわかに私達の知名度が上がり始めているみたいで、市のお祭りのイベントの一環として765プロに依頼が来たんですって。
そして、検討の結果一人は私に決まったって訳。
やん、伊織ちゃんってばやっぱり隠しても隠しきれない魅力があふれ出ているのね。
ペアってのが気になるけど、一気にアイドルらしさがアップだわ!
まぁ、誰が組んでも、それなりに私のフォローは出来るでしょ。
私の相手の子はラッキーね。
「おじさま、ぜひやらせてください!」
「うむ、君ならそう言うと思っていたよ」
「で、もう一人って誰ですか?」
私はわくわくしながら聞いた。
うーん、やよいとなら元気なステージが出来そう。響も悪くないわね。
亜美真美は…ちょっと私の方が押されそうだわ。あ、律子も意外にいいかも。
雪歩は…ちょっと舞台に立つのは早そうだわ。
それなら…。
「千早君だ」
え?
「…はい?」
あれ? 聞き間違えた?
「君とペアを組むのは、千早君だよ。一ヶ月後がステージだ。さぁ、忙しくなるぞ! さっそく午後、千早君が来てから打ち合わせを始めよう!」
「…え?」
「千早ちゃんとなら歌はバッチリね。さぁ、頑張りましょう!」
小鳥がファイト、とガッツポーズする。
でも、その声は殆ど聞こえてなかった。
「千早…と?」
私は自分で自分の顔がうっすらと曇ってゆくのが、嫌という程に分かった。
そして、そんな私を見て、さて、と社長が神妙な顔をしていた事なんて、すっかりてんぱっていた私が、分かる訳が無かった。
四へ Top 六へ

