
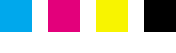

Idolm@ster 小説『歌姫咲く花の園』
三
765プロに私が籍を置いて二ヶ月程過ぎた頃の事だった。
みんなともそれなりに知り合えたし、仲も良くなったと思っていた。
でもまぁ、それでもやっぱり馬が合わないとまでは言わないけど、ちょーっと感覚が合わない相手って言うのは居る訳。
会って二ヶ月じゃまだまだほんの知り合い程度だから、それこそ本当にわかり合えるのはずっと後になってからって言うのが普通なんだと思う。
実際本当に仲が良くなったのは後になってからだったしね。
だから、あの時にああいう事があったのは、必然と言えば必然だったのかもしれない。
「なーんか、思っていた以上に地味よねぇ」
その日の午前中。
特に用は無かったけど、とりあえず顔を出した日。
私は事務所のソファーでうさちゃんの頭に顎を乗せながらぶつくさと呟いていた。
「え? どうしたの? レッスンがうまくいかなかったとか? 何か友達関係で悩みとか?」
小鳥が机から身を乗り出して問いかけてくる。
あんた、こういう話には本当食いつきいいわよね。暇ならゴシップ記者にでも転職したら?
「いやいや、あくまでもみんなの健康管理とかの為よ。暇じゃないわ。体調管理、メンタルケアは事務員の勤め! 他意は無いわ! ホントよ?」
「はいはい。こっちも別に食いつきたくなる話題じゃ無いわよ」
「それでもいいわ。どうせ暇だもん。オレンジジュース買ってくるから聞かせてよ」
やっぱり暇なんじゃない。
「はい、百パーセントオレンジジュース」
小鳥が、ちゃんとグラスに注いで氷を浮かべてくれた。
「ありがと。まがいものだけどね」
「まぁまぁ、伊織ちゃんが頑張れば生のオレンジジュースも飲み放題になるから。ね?」
げ。
やぶ蛇だったかしら。
「で、地味って何が?」
「あー、えっとね、要はぱっとしたお仕事してないわよねーって話。デビューしてないから当然だけど、それでも何かしらそろそろ活動の一つもできないのかしらって思ったの」
一口飲んでから小さく溜息をついた。
うーん、この濃縮還元にちょっと慣れてきた自分が悔しい。
「成る程、まぁそうよね。765プロ開設から三ヶ月。今のところ、みんなの主なお仕事はボイスレッスンやダンス、一般教養とか礼儀作法のお勉強だもんね」
「立場は分かっているけど、なーんか同じ事の繰り返しでやりがいが見いだせないのよねー」
はぁ、と頬杖を突く。
ホント、分かってはいるんだけどね。
「うーん、今のところ表らしい表に出たのはあずささんくらいだし、まだまだお仕事らしいお仕事は少ないもんね」
「はぁ!?」
私は自分でもびっくりするような声を出してしまった。
「ぴ! お、驚いた! な、なに? なに?」
小鳥は一鳴きして飛び上がる。あんたほんとに鳥か何か?
「小鳥、今なんて言った?」
「え? 驚いた、って」
「その前! あずさが何ですって?」
「え? あ、ああ。あずささんのお仕事の話?」
「仕事あるんじゃない! 何で私に回さないのよ! やらせなさいよ! やってあげるわよ!」
私は身を乗り出して小鳥の鼻っ面まで近づく。
「そ、それは無理よ…」
「何が!? 何で!?」
無理と言われたのがカチンときた。
自分の鼻を小鳥の鼻にくっつけて睨み付けながら問い詰める。
「だ、だかはね、あふさはんのおひごとは、こどもひょーのしかひだっはのよ」
「こどもひょー?」
「そふ。ようじむけばんぐひの…」
「ききづらひはよ!」
「い、いほりひゃんのはながくっついてるかはよ!」
「あ、そっは」
そう言えばそうね。
考えてみたら小鳥の顔が妙に近いわ。
甘い香りがする。あんたチョコ食べてたでしょ。
「やぁやぁ、仲が良くて結構結構」
そこへ聞き慣れた声が飛び込んでくる。
「社長、おはようございます」
「おじさま、おはようございます」
私たちはほっぺをくっつけた状態のまま挨拶した。
「うむ、おはよう。今日もいい天気だ。小鳥君も伊織君もすっかり馴染んで結構結構。まるで姉妹みたいだよ。けっこう似ているしね」
「え?」
「え?」
その言葉に、私と小鳥はそうかな? と思わず互いに顔を見合わせようと振り向き合ってしまった。
ほっぺがくっついている事を忘れて。
だから…つまり…。
私の唇に、何かが触れた。
ほんの、ほんのちょっと。
「……」
「……」
「きゃああっっ!!」
「ぎゃーーーっっ!」
「はっはっは、いやいや本当に仲がいいね。眼福眼福」
「し、社長! か、からかわないで下さい!」
小鳥が赤くなりながら否定する。あんた、否定するなら顔赤くするのもやめてよね!
「ぺっ! ぺっ! そ、そうよおじさま! 私が小鳥と何かあるみたいな言い方はやめてください!」
「ぺってひど?い!」
割と本気で悲しんでいる小鳥。何? あんた、そっちもOKな訳?
ああ、なんかチョコの味がするし。
「五月蠅い! 言っておくけど今のはノーカウントよ! 誰が何と言おうとノーカウント! 小鳥! 分かってると思うけど他言無用よ! 余計な事言い触らしたら水瀬家総力を挙げてあんたを…」
私はずい、と小鳥に顔を近づける。
「え?」
只ならぬ雰囲気に今度は身をすくめる小鳥。
そんな小鳥の耳元まで顔を寄せ、そっと呟く。
「闇に葬るわ」
「ぴぃっ!?」
本当に鳥みたいに鳴く。あんた江戸屋子猫の弟子になれるわね。
「冗談よ。でも他言無用は本気だからね?」
「わ、分かってるわよぉ…。あはは…。ああびっくりした…」
挙動不審よ。落ちつきなさい。
私は普段のお返しとばかりにぽんぽん、と小鳥の頭を撫でた。
「それで、あずさの仕事って、子供ショーの司会をしたって事?」
私はソファに座り直して話の続きを始める。
さっきの事はさっさと忘れるに限るわ。
「あ、そうそう。あずささん、大学で児童福祉の講義もちょっとかじってたらしくて、丁度ウチに話が来て、それならって事でオーディション受けてもらったの」
「ふーん。そしたら…」
「声とか仕草とかの受けが良かったみたいで、とんとん拍子で話が進んで」
「お仕事ゲット、と」
「そ。評判良かったみたいよ。またお願いしますって言われちゃった。ふふ、お陰でパイプが増えたわ」
「ふーん…。ま、あずさって見た目がああだから子供受けは良さそうよね」
「子供以上に会場のお父さんやお兄さん達の受けが良かったらしいけど」
「…男って…」
私は溜息をついてジュースの残りを飲み干した。
「そうだ、そう言えば伊織君、君もそろそろ、それらしい事をしてみたくないかね?」
机に腰掛けて新聞を読んでいたおじさまが、黒光りするスマイルで聞いてきた。
「え? お仕事ですか!? ドームですか? それとも十万人ライブとか? それとも海外公演?」
「い、いやいや。それは流石に…」
分かってます。ちょっと言いたかっただけです。
そんなに焦らないで下さい。
「ごほん。今の話の通り、あずさ君の仕事は比較的仕事らしい仕事だが、それ以外にも、まずはお披露目、顔を覚えて貰おうと言う意味で、無償が多いがイベントステージでちょっとしたミニライブをいくつか実行中なんだ」
「路上ライブみたいなですか? ゲリラライブとか?」
そう言えば聞いている。
私は興味無かったからスルーしてたけど、実際にやっていたのね。
「いやいや、それよりはもうちょっといいステージだよ。既に何人かはそういったステージでお披露目を始めている。君もそろそろそう言う時期かと思ってね」
「うーん…」
おじさまの言う事は分かるけど…この伊織ちゃんが路上デビューみたいなのってどうなのかしらね?
「社長、おはようございます」
そこへ千早が帰ってきた。あら、今日は来ていたのね。
「おお、千早君、昨日はどうだったかね?」
「はい、最初はまばらでしたが…最後の曲を歌う頃には大体満員だったようです。後でプロモーションの方から詳しくお話があるかと思います」
「ほう、それは良かった。どうだね、伊織君、千早君も昨日ミニライブを行ったんだ。決して華美な場所ではないが、歌がすばらしければ観客は集まってくれるんだよ」
ふぅん、千早もやっていたんだ。
ちょっと意外に思った。
だって、千早は歌に対する拘りが尋常じゃないから、てっきり整ったステージじゃなきゃやらないと思っていたわ。
「社長、水瀬さんもミニライブに参加するんですか?」
「うむ、まぁ、詳しくはこれからだがね」
「おじさま、わ、私はまだどうするかは…」
「水瀬さん」
そこへ千早が近づいて来た。
「…何?」
なんだか苦手って言うか、絡みづらいところあるのよね、この子。
「ライブに興味があるのは結構な事だけど、収録と違って失敗は許されないのがライブよ。お客さんの前に出る覚悟があるなら、練習はこなした方がいいわ。多すぎると思うくらいでようやく最低限、と考えるべきだわ」
「…そうね」
言っている事は至極まともだけど…もうちょっと別の言い方出来ないの?
「ご忠告ありがと」
「忠告と言うより警告よ。水瀬さん、ちょっと歌のレッスンが足りないかもしれないわ」
「…なんでそんな事言われないといけないわけ?」
「レッスン予定はPCや携帯から全員分を誰でも見られるわ。スタジオの使用予約に必要だもの。他の人もそうだけど、どうも歌のレッスンに裂く時間がみんな少ない気がしていたの。いい機会だから言っておいた方がいいと思ったの。勿論私を含めてだけど、みんな、まだまだ練習が足りないわ。絶対に、練習量が必要だもの」
…なんか、イライラしてきた。
「おじさま! 今スタジオあいてますよね? ちょっと行ってきます!」
「水瀬さん!」
「言われた通りレッスンするのよ! まだ何か文句ある!?」
ちょっとトサカにきてた私は噛みつくように問い返す。
「私は…文句なんて…」
千早は逆にさっきの勢いはどこへやらで縮んでいる。
「い、いってらっしゃい」
迫力に気圧された小鳥が萎縮しながら手を振る。
「あの、水瀬さ…」
外に出る直前、聞きたく無い声が聞こえて、私は乱暴にドアを閉めた。
「……」
ドアが閉まり、静かになった事務所で千早は立ちすくんでいた。
「千早ちゃん?」
「小鳥さん、私…駄目ですね」
千早が深い溜息をつき、自嘲気味に言った。
あーもう何よ何よ! なんで千早ってばいつもああなのよ!?
人には人のテンポってものがあるのよ! 自分の都合を他人に強要するのは止めてよね!
ほんとに!
私はもう訳の分からないままひたすらボイスレッスンをしていた。
なんか内容を良く覚えていない。
でも。
「伊織ちゃん、今日は声の響きが一段といいね! お腹の底から力強く発声されてるよ! ブラボー!」
「え?」
ボイスレッスンの講師が妙に褒めてくれた。
あら、今日は実力通りの評価をもらえたみたいね。
にひひっ♪
…もうワンレッスン追加しようかしら?
翌日、おじさまから昨日聞いた話の正式な打ち合わせがあった。
千早もやっていたし、みんな何かしら最初はこういうのから始めているらしいので、私もそれに習う事にする。
郷に入っては郷に従え、ね。
やるからにはダントツで集客してみせるわ!
特に千早には負けないわよ!
「千早ちゃんに勝つのは、大変よ?」
「え?」
小鳥がぼそりと言った。
「千早ちゃんのライブってね、みんなそうなんだけど、告知もそこそこだから最初は本当にちらほらとしたお客さん相手に始まるんだけど、一旦歌が始まると、どんどん人が集まってくるんだって」
「そ、そうなの? ふーん」
「その集客率や、あずささんや律子さんと並んで三大巨頭と言われるくらいよ。まぁ、あくまでミニライブレベルでの話だけど。でも、人を惹き付ける歌声なのは本当よ」
そういえば、あずさや律子も歌では抜きん出ているみたいなのよね。
…認めるわよ。事実だもん。
でも、千早が三大巨頭の一角ねぇ。
胸はブービーだけど。
「まぁ、確かにデモCDでもいい歌声だったわね。キレイキレイでいいんじゃない」
「…伊織ちゃん、千早ちゃんにはなんか厳しいわね」
小鳥があはは、と冷や汗をたらしている。
「べっつにー。ただ、何とかは三日で飽きる、みたいじゃなきゃいいけどって思っただけよ」
「…あ、あははははは…」
小鳥、仮にも女の子がそんな引きつった顔してちゃいけないわ。しわになるわよ?
「い、伊織ちゃぁん…」
「まぁ、小鳥君をいじめるのはそれくらいにして、本題だ。伊織君、君にはここでライブを行って貰う。大きな施設だから不満は無いと思うよ。いつでも人も沢山居るしね」
おじさまは予定表とその施設のパンフレットを渡してくれた。
「えーと…。まぁ! 白くて大きくて、素敵! 重厚な建物ね?! 本当! 人も沢山! 集客効果は満点ね! ええと、病床数二百、小児科、外科、内科、リハビリ科、その他諸々で何かあっても安心安心…って! 病院かーい!」
「ナイスノリつっこみだ伊織君!」
「流石はおつきあい長いだけあるわね、伊織ちゃん!」
二人が拍手する。
それはどうもって、ちがーう!
「おじさま! 乗せないで!」
「ははは、いや、すまない。だが、病院も充分に素晴らしいステージだと思うよ。病院にいるのはみんな何かしらの怪我や病気で元気を無くした人達だ。そんな人達を君の素敵な歌声で元気にしてあげる事が出来たら、それこそアイドル冥利に尽きると思わないかね?」
「…はい…」
正論過ぎて反論の余地が一ミリもない。
そうね、そうよ。
あのグレタ・ガルボだって私くらいの歳の頃はデパートで働いていたのよ。
それに比べたら芸能関係の仕事って言うだけで充分恵まれているわ。
「分かりました、おじさま、伊織、喜んでそのお仕事お引き受けします!」
「そう言ってくれると思っていたよ! では、スケジュールを正式に決定して進めるとしよう!」
「はい! 伊織、頑張ります! よろしくお願いしまーす!」
規模はともかく、初めての自分のステージだわ!
恋の病から不治の病まで、この伊織ちゃんの歌声でぜ?んぶ完治させてあげちゃうわよ!
私は、早速ダンスレッスンとボイスレッスンの予定をPCに記入して練習予定を組む。
げ、千早、相変わらず予約が多いわね…。
私は千早の予約付近は避けてレッスンを登録した。
…なんとなく、ね。
「それじゃ、ボイスレッスン行ってきまーす!」
「いってらっしゃい」
私は軽い足取りで事務所を出た。
さぁ、忙しくなるわね!
伝説のスターダムへの最初の一歩だわ!
「なんとかは三日で飽きる、か」
「社長?」
伊織が居なくなった後の事務所。
高木はソファで小鳥の煎れたプライベートブランドのインスタントコーヒーを飲みながら呟いた。
「いや、ちょっとね」
黒光りするスマイルにわずかながら影が落ちている。
「…レポートの事ですか?」
「ああ」
高木は小鳥の机脇の書類棚の鍵を開け、中からファイルを一冊取り出した。
それは千早の業績に関する資料。
「最初のステージの集客率は、確かに律子君やあずさ君と比べても遜色がない。…問題は、その後なんだ」
ぺらぺらとページをめくりながら高木は呟いた。
「律子君やあずさ君に比べ、千早君のステージは二回目以降のリピーター率が、少々…低い」
高木の言葉は重かった。
「はい」
「これがどういう事か、彼女は意味を理解しているだろうか?」
「…どうでしょう? 千早ちゃん、自分の考えはなかなか変えませんから」
「実力はある子だからね」
「そうですね」
「だが、芸能界は実力だけではやっていけない。一足す一が必ずしも二になる世界じゃない」
「…はい。千早ちゃん、最初は音響が不安って、なかなかOKしませんでしたからね。社長が説得してやっと首を縦に振ってくれましたけど」
「まずは、彼女にライブと言うものを知ってはもらえたと思う。それだけでもプラスだ。だが、まだまだ彼女の中では妥協の産物という思いが強いんだと思う」
「その結果が、二回目以降のリピーター率に?」
「私はね、伊織君なら彼女を変えられるんじゃないかと思っている」
「伊織ちゃんが?」
「彼女は、自由だ。いろんな意味で」
「自由…」
自由と言うより我が儘じゃない…かな? と思いつつ小鳥は頷く。
「我が儘だって、魅力の一つだよ」
「え!? あれ? あの、声に出しました?」
「ははは、顔に書いてあったよ」
「ええっ!?」
小鳥は顔をぺたぺたと触ってうそ!? と慌てる。
「とにかく、伊織君もいよいよ他の子達と同じように、本当の客の前に立つ事になる。まずは、伊織君のやる気を見せて貰おう。彼女が本気なのか。育てる才能の芽があるのか、最初の見定めだ」
見定め。
高木は伊織をフォローするとは言わなかった。
芸能界は本人の努力と実力、そして運次第の世界なのだ。
「予定どおり、今回の一連の内容の結果よっては…候補生の取捨選択を行おうと考えている。無論、伊織君を含めてだ」
「…はい」
小鳥は真剣な表情の高木を見て、頷いた。
その瞳は事務員の瞳ではない。
まるで、自分自身も対象にあるかのような、アイドルの瞳そのものだった。
その日の夜。
レッスンも充実していたしお夕飯も美味しかった。
あとはベッドでぐっすりと眠って明日への英気を養うだけ、だったのに。
「……」
ああ、眠れない。
駄目。
駄目だわ。
全然眠れない。
私はベッドの上で横になったまま、いつまで経っても消えない時計の音を聞いていた。
部屋の隅にあるアンティークの柱時計が小さく二回鳴った。
ああもう二時じゃない。お肌に悪いわ。
眠らなきゃ、そう思うのに、思いとは裏腹に頭は冴えきっていた。
大丈夫?
頭の中でその言葉が何千回何万回も繰り返された気がする。
大丈夫よ。
肯定の言葉も同じ数だけ繰り返した。
頭の中に弱気の私と強気の私が居て、終わらない問答を続けている。
なんでこんなに弱いのかしら。
自分で自分が情けない。
転んだらどうしよう。
歌を間違えたら、それどころか忘れちゃったらどうしよう。
お客さんが居なかったらどうしよう。
居ても、つまんなくって帰られたらどうしよう。
不安がこんこんと沸き出して止まらない。
私は体を起こして、ベランダから夜空を見上げた。
「…みんなもこんな風だったのかしら?」
そうかもしれない。
でも、違うかも知れない。
私程不安がっている子なんて居ないだろうな。
「…呆れちゃう。千早なら、あの子なら、普段あれだけ練習しているんだから、本番前の不安なんて無いんだろうな…」
何だかんだ言って、千早の熱意を認めてはいる。
そんな自分がますます小さく思え、伊織は顔を埋めた。
眠らなきゃ。
兎に角横になるだけでもならなくちゃ。
「お月様、伊織のライブで、みんなが楽しんでくれるように、応援してください」
伊織は空に浮かぶ月を見上げて暫く祈り、それからから部屋に戻る。
「うさちゃん、今日は、一緒に寝てくれる?」
伊織はベッド脇の小さなソファーに座っていたうさちゃんを抱きしめ、のそのそとベッドに戻った。
「子供っぽくて…ごめんね」
長年一緒だったうさちゃんからは、伊織に安息感を与える香りがする。
その香りに落ちついた伊織は、ようやく眠りについた。
同時刻。
とある住宅の二階の窓が開いていた。
そこは千早の家。
パジャマ姿の千早が、月を見上げて呟いた。
「…どうか、次のステージも、上手に歌を歌えますように…。みんなに、認めてもらえますように…」
一分以上も月に祈った後、窓が閉じ、カーテンが閉められた。
音はない。
二人の少女の願いを聞いていた空の月は、ただ煌々と夜空に輝き続けていた。
翌日からライブに向けたレッスンが始まった。
まぁ、普段のと特に違う訳じゃ無いけど、目標が明確にあるとがぜんやる気が違う。
うん、やっぱり伊織ちゃんは本番向きなのね!
「自曲じゃないのがあれだけど、なかなかいい曲じゃない。この曲も伊織ちゃんに歌って貰えるなんてラッキーよね!」
今日、小鳥から本番で歌う曲の譜面とCDを手渡された。
どうやら今回ライブをする子はみんなこの歌を含めた数曲を必ず歌っているんだって。
所謂テーマソングってやつね。
まぁ、誰よりも私が魅力的に歌ってみせるけどね。
残りの曲は伊織ちゃんに相応しいものを何か好きに選んでいいみたい。
この作業って、結構楽しいわね。
「あはは、すごい自信ね、伊織ちゃん」
小鳥が感心したように言う。
「にひひ♪ 当然よ。自信のない曲で、みんなの前で歌える訳無いじゃない」
「うむ、その意気だ。期待しているよ」
そこへおじさまがやって来た。
「あ、高木のおじさま、おはようございます」
「ライブは心を込めてみんなに思いを伝える事が大切だ。頑張ってくれたまえ」
「勿論です。任せてください!」
私は胸を張った。
「それじゃ、これから歌のレッスンに行ってきまーす!」
「いってらっしゃーい」
小鳥が笑顔で見送ってくれた。
…大丈夫よね?
手が震えていたの。
心臓がどきどきしていたの。
気付かれてなかったわよね?
タクシーの中、私は震えの止まらない自分の手を強く握り、早く落ちついて、と念じ続けた。
その時、急にタクシーが止まる。
「きゃあっ!? な、何よ!」
私はシートベルトをしていたお陰でちょっと胸がぐえってなっただけだった。
初めて役に立ったわ、シートベルト。
って、それよりも!
「何? どういう運転してるの!?」
万が一この可愛い顔に傷なんかついたらどうするのよ! 私は勢いのままに怒鳴ってしまう。
「す、すいません! 子供が急に飛び出してきて!」
子供!?
「えぇっ!? だだ、大丈夫なの!?」
「は、はい! 多分! ぶつかってはいませんから!」
「ち、ちょっと開けなさい!」
私は何も考えず外に出て、車の前を見た。
「きゃっ!?」
そこには、パジャマ姿で倒れた男の子が居た。
「ちょ、ちょっと君! 大丈夫!?」
車からは数メートル離れている。
確かにぶつかってはいないみたい。
どうやら、車の前に倒れちゃったって感じらしい。
見た目は五歳くらいの男の子を、私は抱きあげた。
うわ、なんか軽くない? 怪我は…無い。でも、なんだか妙に青白いような…。
「う…」
「大丈夫!?」
「う…うう…」
ど、どうしたらいいの?
「あ…」
男の子が目を開ける。
「気がついた!?」
「…ちょうちょさんだ」
「え?」
「やっぱりちょうちょ…」
そう言って男の子は気を失った。
「ちょ、ちょっと! えっと、あんた! この辺に病院ってあるの?」
私は運転手に問いかける。
隣に来ていた運転手がそこに、と指さす。
「え?」
顔を上げると、目の前が病院だった。
…なんか見た事あるような病院ね。
でも、これで直ぐに運べる、と想ったその時。
「いたぞー!」
病院の方から医者が二人駆けてきた。
ダルマさんとナナフシみたいな、ものすごく特徴的な体型のお医者さんが二人。
そしてダルマさんの方が、私から奪うようにして男の子を抱き上げて、来た速度そのままに戻っていった。
「…なに?」
きょとんとしていた私に、もう一人のナナフシみたいに細身の医者が手をさしのべてきた。
素直に手を取って立ち上がると、医者はこういった。
「君があの子を助けてくれたんだね、ありがとう!」
ふーん、ちょっと髪がぼさぼさだけどなかなかりりしい顔つきね。
「ううん。私は倒れたあの男の子を見ていただけよ? まぁ、ここに知らせようかとは思っていたけど」
「十分だよ。本当に良かった。彼はここの患者なんだよ」
「あ、やっぱり」
「普段は大人しいんだが…待ちきれなかったんだろうな」
「…何がですか?」
「いやね、実は二週間後にここで慰問の…」
ふと、医者の目が私の顔を見つめて固まる。
いやん、伊織ちゃんが魅力的だからってそんなに見つめられちゃ困っちゃうわ。
「水瀬、伊織ちゃん?」
「え?」
何で知ってるの? まだ人前に出てないわよ? ス、ストーカー?
「そ…そうだけど…」
しまった。言わなきゃ良かった! そう思って後ずさった時、医者が言った。
「君に会いたがっていたんだよ」
「え?」
「君のコンサートを、あの子は心から楽しみにしていたんだ」
あ。
そうだ。
思い出した。
ここ、私が歌う病院なんだわ。
二へ Top 四へ

