
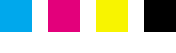

Idolm@ster 小説『歌姫咲く花の園』
二
「え? オレンジジュースも無いの?」
私が765プロで散々なデビューを果たした次の日。
事務員の小鳥の前で私はまた声を上げてしまった。
音無小鳥。
765プロの事務員だけど、なんか事務にしちゃ声がいいのよね。
もしかしてアイドル崩れとか何かじゃないかしらって私はふんでいる。
そのうちみんなに聞いてみようかしら。
「ご、ごめんね、伊織ちゃん、ほら、ウチ小さいから、備え付けの自販機とか無くて、みんな自分で買ってきて共同の冷蔵庫に入れているの」
…違う。
違うのよ、小鳥。
伊織ちゃんが言いたいのはそんなレベルの話じゃなくて…。
「小鳥、違うのよ」
私はため息をつきながら、おでこに指をあててやれやれ、と首を振る。
「え? ひえっ!?」
私は小鳥の両肩にがっしりと手を置く。びっくりした小鳥は声をだして身をすくめた。
「いい? 私が言いたいのはね、この水瀬伊織がオレンジジュースと言ったら、絞りたて百パーセントなの! もちろん濃縮還元なんて論外よ!」
「そ、そうなんだ…。でも、濃縮還元だって百パー…」
「甘い! 甘すぎるわ! いい? 濃縮還元って事は、濃度的に百パーセント以上に加工した原液に何かを混ぜる事で、濃度的に百パーセントに仕立てているに過ぎないのよ。つまり、実際は果汁以外の何かが入っている、混ぜ物のジュースなの。純粋培養で育てられたこの伊織ちゃんがそんなまがい物のジュースなんかで満足出来る訳無いの。分かった? you see?」
「……」
あれ? 小鳥が目を点にしている。
そんな変な事言ったかしら?
「ふむ、なかなかの拘りね。言っている事も間違ってはいないわ」
「ひゃっ!?」
いきなり後から声がしたので、私は思わず飛び上がってうさちゃんを強く抱きしめてしまった。
あ、うさちゃんごめん、苦しくなかった?
「だ、誰? あ、り、律子…。お、脅かさないでよ」
「私は普通に入ってきただけよ。伊織が熱弁に夢中で気付かなかっただけ。ま、驚かしちゃったならごめんね」
そう言ってけらけらと笑ったのは秋月律子。
ぱっと見はアイドル候補生というよりベテランのOLみたいな、スーツ姿の女。
メガネかけているし、この整然とした口調だから、ますます事務員みたいに見える。
「べ、別にあやまらなくてもいいわよ…。はぁ」
会ってまだ二日目だけど、律子はとにかく頭がいい、と思う。多分間違ってないわ。
前日、幼稚園みたいになっていた鬼ごっこを納めたのも律子だった。
そのやり方はちょっと癪だったけどね。
「まちなさーい!」
「いおりんおこったー!」
双子がネズミみたいにはね回って私から逃げる。
いつの間にかボーイッシュな女も面白そう、とか言って加わっているし。
ああもう、何なのここは? 本当に芸能事務所なの?
「いおりん、真美は真美だよー」
「亜美は亜美だよー。よろー」
双子、亜美と真美が走りながら自己紹介した。
「あっそ! って、いおりんって言うなー! 私の名前は水瀬! 水瀬伊織よ! い、お、り!」
「やっぱいおりんじゃーん」
「いおりんだー」
「だからーーっっっ!」
みんなに挨拶するより先に始まってしまった鬼ごっこ。
知的に、おしとやかに、上品にみんなに挨拶して、せめて精神的優位に少しでも立って、遅れを埋めようと思っていたのに、蓋を開ければいきなり、いおりんだの、でこちゃんだの失礼な呼び名の応酬。
私も頭に血が上って、思わず素でみんなを追いかけ回してしまった。
ああ、今考えても顔から火が出そう…。
そんな時。
「はいはい! あんた達、そろそろやめにしなさい! たるき亭の天井が落ちちゃうわよ!」
「あ、それは困るねー。お昼食べられなくなっちゃう」
「んじゃやめー」
「きゃあっ!」
突然二人が止まったから、私は思わずそのまま二人に突っ込んでしまった。
「おっとっと」
二人が一緒に私を受け止める。
二人の明るい笑顔が、びっくりして目を丸くしていた私の目の前に迫った。
「だいじょぶ?」
「いおりん軽いねー」
「あ…ありが…と…」
突然だったので思わず普通にお礼を言ってしまった。
「って、考えたらあんた達がからかったからじゃないの! それと、離しなさいよ! 暑いわね!」
私は二人に一緒に抱っこされるような形で押さえつけられていた。
「えー? もうちょっといいじゃん。いおりんなんだかいいにおーい」
「うんうん、ちっちゃくってやわらかくって、とーってもかわいー。お人形さんみたーい」
お、お人形って…わ、悪い気はしないけど…そ、それより! 子供扱いは嫌よ!
「と、兎に角離しなさい! 高校生だからって、好き勝手していいなんて事無いのよ!」
「へ?」
亜美と真美がきょとんとする。
「な、何よ」
「…いおりん、何歳?」
「…じ、十五。中学三年生よ」
「あー…」
「そう言う事かー」
二人が顔を見合わせてうんうん、と妙に納得して頷きあっている。な、なんか嫌な感じね。
「何よ!」
「あのねー、いおりん、亜美と真美ね」
「十三歳だよ」
「はいはいわか…」
え? 今なんて?
……。
「…え?」
「だから、真美と亜美、中学一年生だよ」
「……」
ち、ちょっと待って。
耳が悪くなったかしら?
ヘッドホンだってオーディオだって変な音では聞いてないわよ。
この二人、顔が私の頭の上にあるわよね?
別にヒール履いてないわよね?
私、縮んでないわよね?
「…もう一回」
万が一の聞き間違いを期待して問いかける。
「ちゅーがくいちねんせー!」
「十三歳だよ。よろー! 仲良くしよーね!」
そう言いつつ、二人は改めて私をぎゅっとサンドイッチ状態にして、頭をなでなでし始めた。
「……」
屈辱の筈なのに、私は思考がとんじゃったのか、暫くなすがままにされていた。
「んっふっふ〜。いおりんかわい〜」
「柔らか〜い♪ それに髪さらさらだ〜!」
「はいはい、亜美、真美、そろそろ伊織を解放してあげなさい。借りてきた猫みたいになっちゃってるわよ」
「……」
「んっふっふ〜。いおりん、これからよろしくね〜」
「いつでもぎゅーってしてあげるよ〜」
「だ、誰がっ!」
「はいはい、伊織、ま、こんな感じでみんなけっこう自由だからさ。あんたも、あんまり自分を作らないで素直になる事をお奨めするよ」
「つ、作ってなんか…」
反論しようとして声が途切れる。だって、そうしようとしていた…。
「私、私は…」
「うん、分かってるよ。いいこいいこ」
律子が頭を撫でて微笑んだ。
ああもう! 今日は何回頭撫でられるのよ!
嫌じゃないけど、子供扱いしないでよね!
あぁ…。
私、世界的アイドルになる為、まずは足がかりとなるこの事務所をビシッとしめるつもりだったんだけど…。
逆に、懐柔されてない?
気のせいよね?
伊織、大丈夫よね?
「伊織、さっそく仲良しが出来て良かったわねー」
律子がにこにこと微笑みながら言う。
「…うん」
抗う気も失せた私は、二人にもみくちゃにされながら頷く事しか出来なかった。
って感じだったわね。
知識的にもそうなんだろうけど、何て言ったらいいのか、頭の回転が早い。
所謂知恵があるんだと思うわ。
だから、こうして相手を上手に宥める事もお手の物。
あんな言い方されたら、これ以上ムキになるなんてばかばかしく思えちゃう。
お陰で私も頭が冷えた。
やっぱり、律子は頭が良いわ。
で、でも、そのうち私だって知的なアイドルになってみせるんだから!
それに比べたら亜美と真美は何なのかしら?
中学一年生で背が私を追い越しているなんてどれだけ成長が早いのよ。
ふたりして小猿みたいに騒がしいし…。
私は普通よ? まぁ、ほんのちょっと平均より身長が低いのは数値的事実として認めるけど…。
はぁ、前途多難だわ。
「それで、伊織はオレンジジュース? 飲みたいの?」
「え? あ! そ、そうよ! オレンジジュース! えっと、私、普段家だとオレンジに限らないけど、大抵その場で絞ったものだけ飲んでいるから、飲みたい時にそれが無いって言うのが、ちょっと気になったの」
「うわ、あんたの家、社長から聞いてはいたけど本当にすごいのね」
律子が感心、と言うより少し呆れたような口調で言う。
嫌味には聞こえないけど…だって普段がそうなんだから仕方ないじゃないの。
「ま、そう言う事なら早速目標が出来て良かったじゃない」
「え?」
「オレンジジュースよ。オレンジジュース」
「も、目標って、そんなのいつだって飲めるじゃないの」
「それは家の話でしょ。伊織、あんたが自分で稼いで、ここにオレンジジュース用のカウンターを作りなさい」
「はい?」
「事務所って言うのは、アイドルのステータスの一つよ。そして事務所が栄えるも衰退するもアイドルの腕一本にかかっているの。分かる?」
律子が眼鏡を指でくいっとあげながら迫る。
「そ、そりゃ分かるわよ。アイドルが売れっ子じゃなきゃ事務所だって儲からないって言うんでしょ?」
「そそ、つまりそう言う事」
「…だから、いい物を飲みたければ、自分で稼げって訳?」
「正解」
律子はぱちぱち、と手を叩いた。
なーんか子供の相手している保母さんみたいだけど…。ま、それはいいわ。
「確かにそうね。トップアイドルを目指すのなら、それくらい自分で用意出来て当たり前よね。なかなかいい事言うじゃない」
私はなんだかむくむくとやる気が出てくるのを感じた。
「一体何から始めようかしら? 演劇とかもいいわね。律子はやっぱり歌?」
「うん。私も、もっと仕事が増えたら事務所で使うノートPCを自分で新調したいと思っているんだ。今ある奴はちょーっとスペックが足りなくってね。流石にセレロンじゃねー。やっぱ今時は最低でもcore2duoくらいは積まないと。出来ればcorei7が欲しいけど。それが手に入るなら、グラフィック性能はまぁ割愛してあげるわ」
「…何を言っているのかは良く分かんないけど、偉いじゃない。流石は事務兼任ね」
「あはは、本業はアイドルってしたいんだけど、今のところは実際事務が多いからね」
律子は参った参った、と頭を掻いて苦笑いしながら言う。
「ま、事務は好きだからいいけど」
でも、その表情はやっぱりどこか寂しさを滲ませている。
「……」
昨日、帰る時におじさまから候補生全員のデモCDを貰って聞いてみた。
すると、当然と言えば当然なんだけどみんなそれぞれ良かったし、律子の歌もとっても良かった。
何て言うのかしら? 歌唱力が抜群なの。
千早ってのも良かったけど、彼女の歌にはちょっと堅さがあるわね。正確すぎる。いい意味での揺らぎが無かった。うん。
それに比べると律子のポップな歌、しっとりしたバラード、聴いた曲はどれもとっても良かった。
声量もあるし、声自体もいい。ダンスだって素敵だったわ。
それに、今の恰好が眼鏡にスーツだから一見OLだけど、実際の所律子はスタイルいいし、顔にしたって、とっても美人。
才色兼備ってこういう事?
正直言って、少し嫉妬してる。
なのに、律子の仕事は事務の方が多い。
これがどういう事かというと、つまりはそう言う事。
「…ねぇ、律子」
「んー?」
なんだか心の奥底に怖いものがじわじわと滲み出て来た、そんな気がして少し恐くなる。
うさちゃんをぎゅっと抱きしめながら、私は言った。
「…アイドルって、簡単じゃないわよね」
思わずしみじみと言ってしまった。
「ん、そうだね。大変だよね。伊織もちゃんと分かっているのね」
律子は神妙だったらしい顔の私を見て、優しく笑ってあたまをぽんぽん、と撫でる。
だーかーら! 子供扱いしないでってば!
「で、目標は決まった?」
「あ、そうそう。勿論それでいくわ! にひひっ♪ さっそく実入りの良い仕事を取ってこなくちゃね。なんか適当なの無いかしら?」
「こらこら、さっきまでの謙虚さはどーしたの? そう簡単にお仕事なんて無いって。第一あんたも私もまだ候補生でしょ」
「あ、そうね。律子、あんたは今までに何したの?」
そう言えば実際何が出来るんだろう。
私は興味本位で聞いてみた。
「聞くも涙語るも涙だよ〜? それでも聞く?」
「え? な、何よそれ。何でアイドルがそんな浪花節みたいな事になる訳?」
脅かさないでよ、と笑って受け流そうとするけど、律子の目は笑ってない。
「…ほ、本当にすごいの?」
「聞く?」
「う、うん…」
律子はそんなに長い話じゃないけど、と言いつつソファーを進めたので据わって話をする事にする。
あ、小鳥、この際ストレートじゃなくていいからジュースお願いね。
「んーとね、私はここに来たのが二番目なんだ」
「一番目の候補生って?」
「春香よ。あの子、募集を見て真っ先にここに来たの。何でも募集を始めた次の日の朝一番で電話してきたらしいわ。小鳥さん、あんまりものすごい勢いで電話してきたから、最初は思わす『振り込め詐欺のお電話はお断りです!!』って切っちゃったんだって」
「はぁ!?」
私は後のデスクでノートとにらめっこしていた小鳥を見る。
私の視線に気付いた小鳥は、見ないで! と顔を真っ赤にしてバインダーで顔を隠してしまった。
…大丈夫かしら、この事務員。
「で、その後もう一度掛かってきて、振り込めでも押し売りでもないから話を聞いてくださいって、必死に話してようやく面接だって分かってもらえたらしいわ」
「…それは、何というか、どっちもどっちね」
勢いのありすぎる候補生候補と対応に問題有りの事務員。
私、ここに籍を置いて大丈夫かしら?
でも…。
なんだか、ものすごく胸が痛い話だわ。
電話一つするのにあれだけテンパっていた私の立場が…。
これだけの勢いで突き進める。
それだけでもすごいわ。
ごめんね春香、特徴が無いなんて思っちゃって。
あんたには根性と料理の腕とドジ属性が立派に備わっているわ。
アイドル方面の才能は知らないけど。
「あの時の事はいい思い出ですよね、小鳥さん」
「い、言わないで〜」
「駄目、あんたが何かヘマする度にこの話は誰かに広める事にするわ」
「伊織ちゃ〜〜ん…」
冗談よ冗談。
そんな生まれたてのヒヨコみたいな弱々しい目で見ないで。
「で、春香の後に律子って訳?」
「そう。私は募集が始まってから一週間後位だったわ。元から歌とか演劇とかに興味があって、自分の実力と本気を試してみたくって」
「そうなんだ…」
律子も自分を試したいんだ。
私は小鳥が持ってきたオレンジジュースを…って缶のままなのね。
ま、百パーセントってだけでも良しとしてあげるわ。
「んっ」
プルに指をかけて力を込める。
ちょっと腕がぷるぷるしたけど無事に開けられた。
別に非力なんじゃないわよ。
引っかかりが悪いから力を入れにくいだけよ。
律子、なにニコニコして私を見ている訳?
私はそれを誤魔化すようにこくりと一口飲んで、それで? と話を続けさせた。
「社長との面談で色々話したわね。履歴書も初めてだったから色々不備がないか不安だったわ。一応写真写りも気にしなきゃ、と思って随分撮り直したのよ。これでもね」
「履歴書?」
そう言ってはっとなる。
私、履歴書は書いてないし、面談もしていない。
「……」
急に居心地が悪くなって思わず俯く。
すると律子は。
「伊織、全部知っている訳じゃないけど、どうやってここに入ったかは大した問題じゃ無いんじゃない?」
「…え?」
ちょっと恐る恐る顔を上げる。
「だってさ、これが突然銀幕デビュー予定として入ってきた、なんて言ったらそりゃ他のみんなはふざけるな、になるよ。でも、伊織は候補生としてだけ、ちょっと違う方法で入ったんでしょ?」
「う、うん…」
「アイドル候補生ってのは、言ってみればアイドルの卵の前。これから卵になって、見事に孵化して、そしてステージって言う大空に羽ばたけるかは今の時点じゃ全然分からないのよ。入ってやっとスタートラインどころか、スタートラインに並ぶ準備が始まるって言う程度。だから、別に応募締め切りの後に新しい子が来たって、別段ひいきとか思わないわよ」
「そっかぁ…」
そうなんだ。
アイドル候補生、確かに候補って言っているんだから、これからの事は何も保証されていないのよね。
全ては自分次第。
うん、そうよね。
「……。え?」
「ん? どしたの?」
「律子、さっき、応募締め切り後って言った?」
「言った」
律子はペットボトルのミルクティーを飲みながら言う。
「…応募締め切り後?」
「そうだよ。あんた、応募締め切りの後の一ヶ月後にここに来たんだよ」
「えぇっ!? ギリギリじゃなかったの?」
私は思わず立ち上がって声を上げる。
「違うよー。だからみんな最初は何事かと思ってあんたに興味が出たんだよ」
「う、うそ…。え? あれ? 書類だと確かに…」
「もしかして、あんた最初の募集要項見てからその後サイトをチェックしてなかったでしょ?」
「う…」
その通りだ。
私は最初にパパから話を聞いて765プロのサイトを見た。
そして内容をプリントアウトして、その後は…思い出したくもないけど、テンパリっぱなしの挙動不審者状態だった。
当然その後サイトなんて一回も見て無くて…。
「あぅ…」
律子がやっちゃったね、と笑う。
「あはは。いおりー、サイトにもちゃんと書いてあったんだよ? 募集要項は応募状況によって内容、期日が変わるから、ちょこちょこチェックするようにって」
「そそ、そういえば…そうだった…かしら?」
私は顔の温度が上がったり下がったりしているような気がして目が回りそうになった。
ああ、何? 何なの?
私は、一体何?
エレガントなお嬢様アイドルどころか、単なるおっちょこちょいになってない? ない?
そう言う事だったんだ。
だからあの時、パパは高木のおじさまに無理を言って私を押し込んだんだ。
あの時…締め切りが過ぎていたのに、それに気付かないでおろおろしていた私を見かねて、パパは…。
私、ダメダメじゃない…。
どっと力が抜け、私はソファーに突っ伏してしまった。
「だいじょぶ?」
「…うん、自分に呆れただけよ」
あはは、と笑うつもりがため息しかでない。
そんな私を見た律子は、向かいのソファーからこっちにやってきた。
そして。
「ほいっと」
「ひゃっ」
軽々と私の頭を持ち上げ、さっとソファーに座って頭を膝に載せる。
「…律子?」
私は律子に膝枕された形になってしまった。
「……」
「大人しいね」
もっと暴れるかと思った、と律子が頭を撫でる。
「なんか…ちょっと、疲れたみたい…」
ここに来てから私、なんだか駄目出しばかりされている気がする。
私、自分で思っているよりずっとダメな子だったの?
落ち込んでいる私に律子が優しく語りかけた。
「伊織はいい子だね」
「…皮肉ぅ?」
思わず憎まれ口。
「違うわよ。自分の事でそれだけ落ち込むって事は、本当に一生懸命だったからでしょ? 私だってそうだけど、あんたもまだまだ成長期。体も精神も、大人にはほど遠いんだからこれから頑張ればいいのよ」
「それは…そうかもだけど…」
「それでいいの。子供の時の恥ってのは、大人になってから最高の肥やしになるんだからね」
「それ、誰かの科白?」
「ううん、今考えた」
…やっぱり頭良いな、律子は。
「…そう言えば、さっきの話は?」
「あ、私の聞くも涙語るも涙、の事?」
「うん」
「なーんにも無い」
「え?」
「何にもない。それだけ」
「何も?」
「そう、それって恐いよ。まだ自分は何もしていないし、出来ないって言うのは。今までにやったのはレッスンだけ。他人様の前に出る事は一度もやってないの。まぁ、当然だけどね。今の私はただの一般人。アイドルなんて候補生って付けても言うのもおこがましいからね」
「…そっか。そうかもね」
何もない、って言う怖さ。
確かにそれは恐いかも知れないわ。
私だって、これから先、何も出来ないまま時間が過ぎたらと思うと…。
背中がぞくりと凍る。
言いようのない不安が恐くて、私は頭を載せている律子の腿をそっと掴んだ。
「ん、伊織、頑張ろう。夢があるから、お互いここに居るんだもんね」
「…うん」
大人だな、律子は。
もうちょっとだけ膝を借りよう。
そう思っていた時、私のお尻に突然何かが乗っかってきた。
「ひっ!?」
びっくりして顔を上げると、何とそこにはあろう事か私のお尻を枕にして寝息を立てている…。
「み、美希っ!?」
「むにゅ〜。おっきな桃がおいしそうなの〜。うふふ…」
な、何の夢見てんのよっ!
それより、人のお尻を、この伊織ちゃんのお尻を勝手に枕にするなんて何様よ!
て言うか初めて会った人に向かって、その次の日にこういう事する!? 普通する!?
ど、どきなさいよ! こらっ!
「やっぱいい子だね」
「へ?」
突然律子がしみじみと言う。
「だって、本気で起こさないじゃない」
「! べ、別に気を使っているんじゃなくて! お、大声出してうっかり他の子達にこんなとこ見られたら…。い、伊織ちゃんのイメージに傷がつくでしょ!」
「あら〜、みんな重なっておねむですね〜。可愛い〜。うふふ」
げ。
声のした方を見ると、そこにはとろけそうな笑顔のあずさが居た。
ああもう、よりによってこの天然に見られた!
その目は明らかに小動物を慈しむ目。
ちょっと待ちなさい! この伊織ちゃんを小動物扱いなんて許さないわよ!
自分が小動物並みの方向感覚しか持ってないくせに!
聞いたわよ! 事務所から駅までの数百メートルの距離を辿り着くのに半日かかった事があるって!
「み、美希もちょっと! 起きなさい! 動けないでしょ!」
「きょうのおにぎりや〜らかいの〜」
ああもうダメだわこの子。
「動かなくてもいいですよ〜。あ、ちょっとスナップ取らせてね、伊織ちゃん」
いつの間にか横に並んだ小鳥が、慣れた手つきで一眼レフを構えている。て言うか、既にバシャバシャとシャッターを切っているじゃない!
「ちょ、ちょっと! いいなんて言ってな〜い!」
あんた! 何よそのごっついカメラは!
それ、普通女が持ち歩いているカメラじゃないわよ絶対!
と、とにかくもう、これ以上面倒が増えな…。
「あ、いおりんまくらだ〜」
「いいな〜。真美もお昼寝したいな〜」
これ以上来るなああっっっ!
こうして、結局765プロ出社二日目は帰りまでずぅっとソファの上でもみくちゃにされ続けてしまった。
帰り道。
ああ…。
何て言うか、言いようのないこの脱力感と言うか疲労感は何?
あそこは本当に芸能事務所なの?
「お嬢様、お疲れですか?」
帰りの車の中で新堂が心配してくれた。
「味方はあんただけよ…」
「はい?」
「何でもない…。ちょっと、眠らせて…」
その後、私はすぐにすぅすぅと眠ってしまった。
明日もこんな感じかしら?
はぁ、先が思いやられるわ…。
明日…かぁ…。
事務所が開くのは…何時から…だったかしら?
渋滞前には…行きたい…わね。
明日も…みんなと…いっしょ…に…。
「お嬢様、何とも満足げな寝顔をされておられる…。良い事があったのですな」
信じられないけど、新堂はその時の私の寝顔を見て、そう言ったらしい。
しかも楽しげな寝言まで言っていたとか。
…嘘でしょ?
一へ Top 三へ

